私も連鎖解析について一部執筆した「アグリバイオ2021年4月号」が届いたので、311の本棚に入れてます。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281697603/next/
Taxonomic revision of the South Asian River dolphins (Platanista): Indus and Ganges River dolphins are separate species
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12801
hard for japanese timezone but interesting
https://www.youtube.com/watch?v=lX4d12nT9PM&ab_channel=SatijaLab
Phylogenetic analyses suggest centipede venom arsenals were repeatedly stocked by horizontal gene transfer
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21093-8#Abs1
Tracing the genetic footprints of vertebrate landing in non-teleost ray-finned fishes
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421000891
African lungfish genome sheds light on the vertebrate water-to-land transition
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421000908
肺魚に関しては、この論文がでる直前にAxel MayerがNatureに出した。
Giant lungfish genome elucidates the conquest of land by vertebrates
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03198-8
Hi-C使っている研究がとても増えてきたので、当研究室でもHi-Cの外注先などを見つけておいたほうが良いような気がします。
eDNAir: proof of concept that animal DNA can be collected from air sampling
https://peerj.com/articles/11030/
it should work but sounds diffcult to apply for environmental studies compared to aquatic research because there is no closed system
健康なヒトの筋肉の通常の老化に伴うトランスクリプトームの変化。単純な論文ですが、普通の老化の基礎データとして押さえておくべきかな。
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22168-2
他群RNA-seqの解析例としてもいいですね。まあ時系列データだから性質が少し特殊ですが
多群
👍
Sub-nucleosomal Genome Structure Reveals Distinct Nucleosome Folding Motifs https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418316283?via%3Dihub
Proximal molecule biotinylation by a BirA2-conjugated target protein showed proteomic responses to the heart regeneration in zebrafish
https://elifesciences.org/articles/66079
いや、硬くて(biopsyが難しい)大きい(場所による影響が出てしまう)筋細胞には適用難しい?
なんか細胞に傷つけちゃう影響が無視できなそうで微妙だなと思いました
そうですね。でもライブイメージングのようにRNA-seqができるというコンセプトが面白いと思いました。いつか非侵襲的かつ網羅的に遺伝子発現を観察できる手法が開発されるんだろうか?
in vivoで観察するとなると今の技術ではレポーターアッセイですかね。使える色の数がスケールしないので、なにか新しいブレークスルーが必要そうです。
あとは発現レコーダーがそのアイデアに近いですかね。in vivoでの観察はできませんがあとから発現情報を再構築するみたいなのは取り組みがいくつかあったと思います。
すべての遺伝子の3’領域に正確にバーコードを挿入できる技術があればgRNAとその編集ターゲットを挿入して転写が起きたときバーコードに変異が入るようにできたりするかな?とかなんとなく思いますが…笑
durable expression suppressor/activator by methyltransferase/demethylase fused dCas9
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00353-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421003536%3Fshowall%3Dtrue
FISHを行うならば、glyoxalを添加すると染色像が鮮明になるという報告です。
https://rnajournal.cshlp.org/content/early/2021/04/12/rna.078671.120.abstract
PicoPLEX DNA-Seq (Picoseq), DOPlify, REPLI-g and Ampli-1 WGA
GenomiPhi, REPLIg, TruePrime, Ampli1, MALBAC, and PicoPLEX
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5313163/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/443754v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/186940v1.full.pdf
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
精子シングルセルだとセントロメアの組み換えが起きないので、卵子を使えば良いのではと思ったりしました。でも卵子は受精するまで2Nのままで、受精して初めて極体放出して1Nになるというのを知って断念しましたが、既に8年前に極体放出させた卵子を使った連鎖解析がされていたとは。。。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867413015262?via%3Dihub
IlluminaでもMGIでもない別のシーケンサーが2020年に発売されていたようです。
米国 GenapSys™(ジナップシス)社より発売だそうです。
https://up.n-genetics.com/sp_contents/24832/
1GB8万円くらいして高いので使い道は限定されそうですが、本体価格が260万円らしいです。
IonTorrentに似た原理のようですが、1塩基ずつ合成するようなのでクオリティはIllumina並みになっているそうです。(IonTorrentはパイロシーケンスだったためクオリティが悪かった)
今年中にスループット10倍のチップが発売されるそうなので、そうなると面白いかなと思いました。(これで新しいチップを発売しないと正にIonTorrentと同じことを繰り返してしまうわけですが、さて…)
Iterative cryosectioning by different angles enables 2D reconstraction of gene expression patterns. They applied this to a brain of non-model organism (lizard).
https://www.nature.com/articles/s41587-021-00879-7#Bib1
先ほどHi-Cの受託解析を行っているレリクサの方とお話ししまして、正式な見積もりはまだですが、1サンプル当たり50万円弱でHi-Cを行えるとのことでした。こちらから送るサンプルは新鮮な凍結組織で20 mg x 5くらい必要とのことでした。Hi-Cのデータ解析は3D-DNAなどのソフトウェアで簡単に実行できます。(ただし、その結果が正しいかというと結局のところよくわかりません。)納期は2~3か月だそうです。
Hi-Cでのゲノム解析に興味がある方は、下記で紹介されている論文等を読んでみてください。
==============================
東京大学 農学部
吉武 和敏 様
お世話になっております、レリクサ研究開発部の保坂と申します。先ほどは貴重なお時間をいただきありがとうございます。
面談中にご説明しきれなかった点についていくつか補足いたします。
まず、組織の違いがHi-Cライブラリのクオリティに与える影響についてですが、下記論文のFig.3Bにある通り、
核を抽出した段階ですでに幾らか断片化されてしまうような組織では、内在性ヌクレアーゼの影響などによりうまくHi-Cライブラリが構築できないようです。
また、面談中に肝臓は不向きとお答えしましたが、liverの方がむしろよいライブラリが作られており私の勘違いでした。不正確な情報をお伝えしてしまい申し訳ありません。
https://academic.oup.com/gigascience/article/9/1/giz158/5695848
Hi-Cのライブラリ調製に用いられている組織としては、魚類では筋肉や血液がよく使用されているようでした。
https://academic.oup.com/gbe/article/13/2/evaa272/6050813
http://www.zoores.ac.cn/article/doi/10.24272/j.issn.2095-8137.2020.264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6841922/
次にデータ量についてですが、ゲノムサイズ1Gbあたり100M read pair 以上が推奨となっていおりますので、ご参考のうえデータ量をご検討いただければと存じます。
https://dovetailgenomics.com/wp-content/uploads/2019/03/Hi-C-kit-_ProductHighlight_WEB.pdf
またご不明な点がございましたらご遠慮なくお申し付けください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
保坂
A widespread pathway for substitution of adenine by diaminopurine in phage genomes
https://science.sciencemag.org/content/372/6541/512
Some phages incorporate diaminopurine (Z), which forms three hydrogen bonds with (T) (and I guess maybe (U) too), instead of adenine (A) into their genomes and this group determined the gene (purZ) and the pathway for producing Z as well as the prevalence of putative Z genomes (not Z-DNA) in public data. The Z genomes are more resistant to restriction enzymes that target AT rich RE-sites.
Noncanonical DNA polymerization by aminoadenine-based siphoviruses
https://science.sciencemag.org/content/372/6541/520
This group identified some phage DNA polymerases that preferentially incorporate Z into DNA. The polymerase genes are usually clustered with purZ (Z synthesis gene) on the genome.
I tried using the first ~29 amino acid residues (which contains the conserved catalytic serine motif) of a purZ gene from the first paper to TBLASTN the contig DB's I created (Tama River and Ofunato Bay) and Yoshitake sensei's Sendai Bay db to see if these are in some of our data too. I got a couple hits (15) in the Tama River db, but found it weird that I only got one hit in the Sendai bay db and one hit with a high evalue (8.4) in the Ofunato bay db because actually the first description of a Z-genome was from a 'cyanophage' which infects a marine cyanobacteria..
I also wonder how the host bacteria RNA pol transcribes this kind of Z-genome, and if/when these phages become prophages, does that mean the host then has hybrid Z-containing DNA..
ナノポアのUltra-Long DNA用のシーケンシングキットなんて出ていたのですね。
https://store.nanoporetech.com/catalog/product/view/id/509/s/ultra-long-sequencing-kit/category/28/
ゲノムをナノポアで読む人たちはこっちを使ったほうが良さそう。12万円で何回分なのだろう・・・
ナノポアでゲノムを読みそうな人は、リンク先のプロトコールを読んでみて、何回分なのかとか、他に必要なキットがあるのかなどを調べてみてくれると発注しやすくなります。
- Kazutoshi Yoshitake
- ナノポアのUltra-Long DNA用のシーケンシングキットなんて出ていたのですね。
https://store.nanoporetech.com/catalog/product/view/id/509/s/ultra-long-sequencing-kit/category/28/
ゲノムをナノポアで読む人たちはこっちを使ったほうが良さそう。12万円で何回分なのだろう・・・@西脇和哉 ナノポアでゲノムを読みそうな人は、リンク先のプロトコールを読んでみて、何回分なのかとか、他に必要なキットがあるのかなどを調べてみてくれると発注しやすくなります。
吉武先生
ありがとうございます。
Visiumも固定標本対応のキットが発売されるようです。フレッシュな組織をとるのが難しい生物種には良いと思います。
https://pages.10xgenomics.com/wbr-2021-05-event-ra_g-p_visium-ffpe-launch-jp_lp.html?src=sales&utm_medium=sales&lss=email&utm_source=email&cnm=wbr-2021-05-event-ra_g-p_visium-ffpe-launch-jp&utm_campaign=wbr-2021-05-event-ra_g-p_visium-ffpe-launch-jp&useroffertype=event&userresearcharea=ra_g&userregion=apac&userrecipient=customer
- Kazutoshi Yoshitake
- ナノポアのUltra-Long DNA用のシーケンシングキットなんて出ていたのですね。
https://store.nanoporetech.com/catalog/product/view/id/509/s/ultra-long-sequencing-kit/category/28/
ゲノムをナノポアで読む人たちはこっちを使ったほうが良さそう。12万円で何回分なのだろう・・・@西脇和哉 ナノポアでゲノムを読みそうな人は、リンク先のプロトコールを読んでみて、何回分なのかとか、他に必要なキットがあるのかなどを調べてみてくれると発注しやすくなります。
承知しました、長いDNA用に特化したものがあるということなんですね、詳細調べておきます、ありがとうございます!
Genetic and spatial organization of the unusual chromosomes of the dinoflagellate Symbiodinium microadriaticum
https://www.nature.com/articles/s41588-021-00841-y
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20210518/
駿河湾に生息するオンデンザメの個体数は約1150個体と推定されたそうです。
ニシオンデンザメの遊泳速度の遅さは生息する海域の低水温によって代謝が低下するからではないかと言われてきたが、今回調査した海域の水温等から視覚的相互作用仮説(Visual Interaction Hypothesis)で説明される可能性を示した。
プレスリリース少し見ただけなのでこの仮説がよく分かりませんが、代謝低下だけではないようです。
(一個上の僕が上げた論文が原著論文です、参考までに)
VisiumがFFPEサンプルにも対応ということでウェビナーに参加してきましたが、
mRNAをキャプチャするのはポリAではなく、あらかじめ設計したプローブということで、
RNA-seqというよりはマイクロアレイのようなものになるようです。ですので、
デメリット
1.現在ヒト、マウス用プローブしかなく、それ以外の生物種に対応していない
2.プローブに設計された遺伝子の発現しか観察できない
3.SNPsやスプライシングバリアントなどの解析はできない
メリット
1.ホルマリン固定された数年前のサンプルでも解析可能
2.フレッシュサンプルの解析に較べて、tissue optimizationがないなど操作が簡単
非モデル生物で使うのは難しそうですね。ゼブラフィッシュなどのモデル生物であれば、将来対応する可能性はあるそうです。
Increasing jojoba-like wax ester production in Saccharomyces cerevisiae by enhancing very long-chain, monounsaturated fatty acid synthesis https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-019-1098-9
https://www.nibb.ac.jp/pressroom/news/2021/05/27.html
これ村さんがやってたのと同じ種でしたっけ?
ヒラミルミドリガイだった気がします
さっきそのプレスリリース見てました。
スミスさんの言う通り、ヒラミルミドリガイだと思います
私も今読んでました笑
さて、バクテリアだったーとまで解明されたのかどうか。。。
詳細なプレスの方を読んでみましたが、この論文を元に議論するとより面白いストーリーになりそうに思いました。水平伝播ではないことがわかったけど、原因は不明だ!と前振りしてくれているので、実はバクテリアが関わっているかも?というのは興味を持ってもらえそうかなと。彼らもじきに気がつくでしょうけど。
宣言×→制限〇
↑のelifeの論文通しで読んでみましたが、比較ゲノム解析で考慮すべきツールのバイアスなども丁寧に議論していてとても勉強になりました。うちのラボでこういう系の研究している人多いし全員読んだほうがいいと思います。
特にFig4,5あたり
あとホモロジー検索してるだけでこんだけFig作れるのかというあんまり本質的じゃないところも勉強になりました
elifeの論文ってどれになるのでしょう?直前はnature系列のものですよね。
あ、プレスリリースしかのってなかったか
This idea looks a bit similar to our envDNA thing and I feel cell-free DNA studies coupled with DNA barcodes might be interesting in terms of cellular dynamics such as disease progression.
https://www.nature.com/articles/s41587-020-00775-6
プロジェクト終了して5年ほど経ってますが、ようやく論文にすることが出来ました。メタゲノムデータベースを作ったという論文です。
https://www.nature.com/articles/s41598-021-91615-3
👏

Congrats, sensei!

Congratulations, Sensei.!

Congratulations
良いニュースですね!これを機会にホームページも更新しますか。いくつかアップデートする情報があるように思います。
- 満山進
- 情報をお願いします。
ありがとうございます。学会発表などありますが、自分でアップしておきます
FFPEサンプルのウェビナーがあるようです
- Shigeharu KINOSHITA
- ありがとうございます。学会発表などありますが、自分でアップしておきます
WordPressの編集方法を下記にまとめました。
http://www.suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/blog/internal/edit-blog/
木下先生、浅川先生は既に編集者として登録してありますので、簡単に業績のページなど変更できます。
- Ryo Yonezawa
- FFPEサンプルのウェビナーがあるようです
先にあったウェビナーに参加しましたが、FFPE対応のVisiumは、ポリAでなく予め設計したプローブでRNAをキャプチャーし、しかも読むのはプローブの配列ということで、プローブが設計されているヒトとマウスにしか今は対応していないそうです。マイクロアレイみたく自分でプローブ設計できるようになれば非モデル生物にも広がる可能性がありますが、、
- Shigeharu KINOSHITA
- 先にあったウェビナーに参加しましたが、FFPE対応のVisiumは、ポリAでなく予め設計したプローブでRNAをキャプチャーし、しかも読むのはプローブの配列ということで、プローブが設計されているヒトとマウスにしか今は対応していないそうです。マイクロアレイみたく自分でプローブ設計できるようになれば非モデル生物にも広がる可能性がありますが、、
そういえば参加されていましたね。 失念しておりました。
情報ありがとうございます。思い出しました。
こういうのもあるらしい 虫だけど
https://www.pnas.org/content/118/25/e2103957118
- Kijima Yusuke
@Ryo Yonezawa こういうのもあるらしい 虫だけど
https://www.pnas.org/content/118/25/e2103957118
共生生物がいないと育たないっていう生き物は聞いたことありましたけど、ちゃんと調べられているのは初めて見ました。読んでみます、ありがとうございます。
https://www.nature.com/articles/s41563-021-01021-3
Random access DNA memory using Boolean search in an archival file storage system
it looks more like a hard disk than conventional DNA storage methods
明後日、大気海洋研究所主催の環境DNAに関するワークショップがあり、私も7分くらい発表します。
https://shibuya-qws.com/oceandnatech2021
MiFish系の研究者も数多く発表すると思うので、是非ワークショップを聞いてみてください。
Individual haplotyping of whale sharks from seawater environmental DNA
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.13451
村さんのです
ミノを持つ種はウミウシの多くの分類群に存在するようです
Dinucleotide encoding for DNA barcode is a cool idea though it can only deal with sequencing errors, not for oligo synthesis errors etc. But especially in case of nanopore sequencing, it’s worth considering if you want to use barcodes with nanopore.
https://www.nature.com/articles/s41587-021-00965-w
ちょうど今、ナノポアで読んだ10%くらい間違っているUMIタグをどうやって補正しようかなと思っているところだったので、面白いと思いました。ランダムにUMIタグを合成するのに、二塩基ずつ同じ塩基を入れることができるのですね。でも、今自分のデータを見ている感じだと、二塩基連続したりするとより間違いやすくなっているから、むしろ逆効果なのかもとか思ってしまいました。(論文をちゃんと読めていませんが、どこかで検証していたらすみません。)
正しいUMIタグ配列がやっぱり一番多く出てくれるので、この論文でも正しいUMIタグをもとに、近いUMIタグを補正しているようで安心しました。ナノポアの場合、間違いはINDELが多いので、もしUMIタグを13塩基入れていて、UMI部分が13塩基でないのが来たら間違いというのはすぐに分かるので、補正対象は比較的わかりやすいです。
About the comments about bacterial sRNA's in the seminar today, here is one recent review on sRNA's focusing on the similarities/differences between Gram+ and Gram- bacteria.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1874939919302688
Also here is a review about outer membrane vesicles (OMVs) from bacteria used to transport proteins and nucleic acids.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tra.12488
And here is an interesting paper, where they theorized that a Gram-negative bacteria, Psuedomonas, could deliver sRNA's to eukaryotic host by OMVs and that the sRNAs could target and suppress the MAPK signaling pathway. They showed some indirect evidence of this interaction with the MAPK pathway that seems pretty convincing, but I would be much more convinced if they showed direct interactions of the bacterial sRNAs with the host target mRNA's.
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005672
- Andre Lanza
- About the comments about bacterial sRNA's in the seminar today, here is one recent review on sRNA's focusing on the similarities/differences between Gram+ and Gram- bacteria.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1874939919302688
Also here is a review about outer membrane vesicles (OMVs) from bacteria used to transport proteins and nucleic acids.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tra.12488
And here is an interesting paper, where they theorized that a Gram-negative bacteria, Psuedomonas, could deliver sRNA's to eukaryotic host by OMVs and that the sRNAs could target and suppress the MAPK signaling pathway. They showed some indirect evidence of this interaction with the MAPK pathway that seems pretty convincing, but I would be much more convinced if they showed direct interactions of the bacterial sRNAs with the host target mRNA's.
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005672
Thanks for sharing the review. It was interesting to know that small RNA-mediated expression control mechanisms are widely present in bacteria.
Pure Systemって、最近はHisタグだったかを合成系の全遺伝子につけることで、逆にHisタグなど余計なタグを目的タンパク質につけることなくタンパク質精製が出来ますよね。
https://www.nebj.jp/products/detail/139
立体構造上、N末やC末が内部に入り込んでいる場合などは、タグを付与することで活性に大きな影響を与えることも多いので、出来たらタグなしの状態で実験するのがベストかなと思っています。
私がやっていたときは、N末とC末それぞれにHisタグをつけるバージョンを用意して活性を比較したりもしていました。
天然のvNARの全長がどうなっているのか理解していませんが、もし天然のタンパク質の配列がN末、C末それぞれ少し伸びているなら、そういった配列を伸ばしたうえで、Hisタグを入れるなどしたほうが良いかもしれません。
https://www.nature.com/articles/s43586-021-00046-x
Cell-free gene expression
ついにタンパク質の3次元構造をかなり高精度に予測するAlphaFoldが公開されたようですね。
https://qiita.com/Ag_smith/items/7c76438906b3f665af38
近いうちに研究室のサーバにインストールします。
https://qiita.com/Ag_smith/items/7c76438906b3f665af38
簡易的にalphafoldを使う方法があるようで、確かにウェブブラウザ開いて10分くらいで予測結果が得られました。
研究室のサーバにalphafoldをインストールしていますが、ダウンロードするDBがデカすぎてまだ終わっていません。ちゃんとインストールした方が精度は良いようですが、とりあえず試してみるにはこっちで良いかも。
https://twitter.com/daphnia_t_ponyo/status/1420727233979707393?s=21
構造ホモロジー検索でDaliというサービスがあるみたい。
Alphafold2と組み合わせると、今までノーヒットのタンパク質でもヒットする場合があるみたい
タグをつける際に、立体構造を見て、リンカーの長さや、そもそもどこにタグを入れるべきか考えていたと思いますが、alphafoldを使うと良い時代になったようです。是非試して見てください。
https://note.com/hattorim2/n/nd0d9bd085f35
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24691-8
High-depth spatial transcriptome analysis by photo-isolation chemistry
CUBICよりも浸潤性が高い試薬があるそうです。
https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Clearlight/index.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=2021._Aug._5th_email_news&utm_medium=email
免疫染色するなら、CUBICよりも、CLARITYのほうが中まできれいに染まっているようですね。
ありがとうございます!
A key metabolic gene for recurrent freshwater colonization and radiation in fishes https://science.sciencemag.org/content/364/6443/886
タンパク質の配列を入力するだけでAlphaFoldを簡単に使えるWEBサービスが登場したようです。
https://www.getmoonbear.com/
Google Colab版のAlphaFoldも簡単に使えましたが、こっちのほうが更に簡単でした。
予測された立体構造のファイル(PDB形式)を入手したら、
DALI
http://ekhidna2.biocenter.helsinki.fi/dali/
MADOKA
http://madoka.denglab.org/
といった構造のホモロジー検索サイトにアップロードして検索してみると良さそうです。
上記の2つは検索のアルゴリズムが違うようなので、結構違うタンパク質がヒットします。
MADOKAのほうは、検索結果が単純なPDBのIDだけなので、PDBのサイトに行って、どういったタンパク質なのか検索する必要があります。
https://www.rcsb.org/
ついでに、アコヤ貝の白色変異体の原因遺伝子候補g26480の立体構造をAlphaFoldで予測して、DALIで構造ホモロジー検索をかけた結果が上の図で、緑色がg26480、黄土色が
https://www.rcsb.org/structure/2IS6
のヘリカーゼです。
一本鎖DNAに結合する部分は特によく構造が似ているなぁと思いました。単純なBLAST検索でもヘリカーゼがヒットしていましたね。
他にもmRNAに結合する
https://www.rcsb.org/structure/2WJY
がヒットしたりしていて、もしかしたらヘリカーゼというよりもmRNAの制御に関わっているタンパク質なのかも?などと思いました。
補足すると、上記のような1500アミノ酸を超えるタンパク質は手元のコンピュータでAlphaFoldを実行しないとエラーになってしまいます。
研究室のサーバでのAlphaFoldの利用方法は後ほどマニュアルを作成します。
https://advances.sciencemag.org/content/7/34/eabg5196
Seadragon genome analysis provides insights into its phenotype and sex determination locus
cool, they also published a similar nature paper about seahorse genome several years ago. This is also good to read
https://www.dropbox.com/s/ib8qq6cmql294y3/seahourse.pdf?dl=0
thanks 👍
m64gにAlphaFoldをインストールしました。また、AlphaFoldを使った検索については下記にまとめました。他にも立体構造を使った便利なツールを知っていたら教えて下さい。
http://www.suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/dokuwiki/doku.php?id=alphafold%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9#alphafold%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%E9%85%8D%E5%88%97%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%A7%8B%E9%80%A0%E4%BA%88%E6%83%B3
just learned some people are trying to use T cell receptor sequences as natural barcodes of T cell clones. This work aligned two cell neighbor graphs generated by gene expressions or TCR sequences, which enables the analysis of clonal dynamics coupled with gene expression profiles. https://www.nature.com/articles/s41587-021-00989-2
先こされてしまいましたね。。。
ゲノム結構小さめですかね?
そうですね。こちらのデータでも400MB強でした。
ショートリードとロングリードだけで染色体レベルのアセンブルまでいけてるっぽい感じですね
まだそこまで読んでいませんでしたが、こちらもBioNanoのオプティカルマッピングでほぼ染色体まで行けてました。アユゲノムはアセンブルしやすいのでしょうね。
ありがとうございます、読んでみます
この論文では、ゲノムを解読した後、GWASによる性決定遺伝子座の絞り込み(このGWASまではゲノムを作るときに連鎖解析をするのでついでによくやりますが)、候補となるamhr2bYの発見(近縁種のゼブラフィッシュの性決定遺伝子がDMRT1なのに、トラフグなどと同じAMHR2なんだ~)、CRISPRによるamhr2bYノックアウト個体の性転換の確認(性転換個体が7/31=23%なのでこれだけが原因ではないのかも?)をやっていて、読んでいて面白かったです。
私たちのデータを加えてより精度の高いアユゲノムv2を作ることになるのでしょうか。
話は変わりますが、日本語専用の3行要約ツールが登場しました。
https://www.digest.elyza.ai/
上の文章を入れると、こんな感じに↓
あんまり要約できていない気が…
- Kijima Yusuke
- https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1009705
海洋大の坂本先生のところですね、、、群馬水試には海洋大の吉崎先生のところの学生さんも来ていますが、野生のアユでやっているんですね。こちらはアユゲノムはメインでなく、アユの寿命特性がターゲットですので、アユゲノムは残念ですが、これを便利に活用してこちらの研究のクオリティを上げるべきでしょうね。
In c.elegans, pathogen derived sRNAs are packaged in retrotransposon encoded viral like capsids and they are transferred to the progenies / other individuals to cause avoidance reactions. Though it’s not directly related to our work, this kind of study is always exciting.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421008813
レトロトランスポゾンはウイルスの祖先だと言われますが、まさにそんな機能があるのですね。
入ってきたトランスポゾンを生存戦略に使ってるというのもまた面白いですね
https://www.nature.com/articles/s41588-021-00914-y
The bowfin genome illuminates the developmental evolution of ray-finned fishes
300k scrna for planarian regeneration
https://www.nature.com/articles/s41556-021-00734-6
プラナリアでできるなら、ヒラムシでもscRNAできそうに思えてしまいますねw(明確な標的部位を見つけてからですが…)
にしても、300k cell はすごいですね
全然できると思うけど何がしたいか次第だな〜
split-poolってやり方なら100k以上読めるけど、今回Nextseqで読んでるっぽいのでカバレージ足りてるのかちょっと謎
TTX産生にはやっぱり細菌が関わりそうな感じになってきたので、scRNAが必要かと言われると微妙な現状ですけどもねw
あーたしかにNextSeqって記載されてましたね
scRNAで思いだしましたが、来週の9/7にイルミナのウェビナーで「水産無脊椎動物へのシングルセルmRNA解析適用の実際と工夫」があるようです。
https://jp.illumina.com/events/webinar/2021/webinar-dr-koiwai-210907.html
Geometric deep learning of RNA structure https://www.science.org/doi/10.1126/science.abe5650
スポットが膨大に増えるので、シーケンス代が100倍以上になるかも…?というくらい、コスト増加がとても懸念されるみたい。
ただでさえ高いので販売されても敷居が高そうですね…
たぶん、スライド代はそんなに変わらないのかなと思ったけど、シーケンスが今はHiseqX1レーンで済むのが、100レーン分とか必要になると…
HDSTですかね?visiumの1st authorが2年前にバイオテックに出してました
製品名はVisium HDとなるようです。世界5か所でもうすぐトライアルが始まるとのことで、もう量産化直前の段階なのだろうと思いました。
オリゴが密になる分スライドも高くなるんじゃないかという気がします
ただ五万細胞のシングルセルだとnovaseqかけ始める人が出てきますね
嘘か本当か、スペック的には400倍くらい差が出るらしいです・・・
HDSTは解像度2nmなのでその系列な気がします
デモで見せてくれていた実際のスポットらしいHDのスポットの大きさは、今のVisiumの面積比1/100くらい(長さは1/10)に見えました。
そうすると20umくらいかな?
Visiumは100um間隔で、スポットサイズが55umです。(今日のVisium Dayの問題で覚えたw)
ありがとうございますwデータ見てみたいですね〜
そうですね、1回1千万円以上になりそうですが、見てみたいです。シーケンスデータだけで10TBとかになると解析も辛そう。
maybe good to know for genome assembling
https://www.nature.com/articles/s41587-021-01049-5
既に知ってるソフトかもしれませんが、こないだ参加した研究会ではUMATracker(https://ymnk13.github.io/UMATracker/) というものが使われてました。※メダカ34匹の個体追跡ができているようです(上から撮影しているみたいなので、地頭所がやっているような横からの撮影でどうなるかは分かりませんが…https://www.ipa.go.jp/files/000052822.pdf)
Comparative genomics provides insights into the aquatic adaptations of mammals https://doi.org/10.1073/pnas.2106080118
A practical guide to large-scale docking
https://www.nature.com/articles/s41596-021-00597-z
Simple Cre-loxP based genetic circuits to record the number of cell divisions. Overall not super exciting, but Figure 7 was a bit interesting. Cells experienced numbers of cell divisions tend to enrich ribosome related gene expressions, which is confirmed by the over expression of ribosome subunit.
Aged tissues / individuals are known to highly express ribosomal genes and I wonder this reflects the existence of aged (=much divided) cells.
https://www.science.org/lookup/doi/10.1126/science.abg3029
Simple Cre-loxP based genetic circuits to record the number of cell divisions. Overall not super exciting, but Figure 7 was a bit interesting. Cells experienced numbers of cell divisions tend to enrich ribosome related gene expressions, which is confirmed by the over expression of ribosome subunit.
Aged tissues / individuals are known to highly express ribosomal genes and I wonder this reflects the existence of aged (=much divided) cells.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590921003490?via%3Dihub
I put an wrong link at the previous post, sorry!
溝端くんが「ロングリードWET&DRY解析ガイド」をスキャンしてくれました。
https://univtokyo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/4981384182_utac_u-tokyo_ac_jp/ERoMoZPRxjRNtbcqeMEgH7gB78RUVo57YRzjcQH4zpwV5A?e=i6sHi6
ほかNanoporeでゲノムアセンブルを行う予定の人は、特にP.165〜とP.177〜が普通に出来るようにしておくべきでしょう。
希望者がいれば、その2章の勉強会を行おうかと考えています。
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
岩崎研のメンバーらしき人が分子系統解析の非常に詳しい日本語の総説を書いてくださってます。MEGA以外にも使いやすいツールがあるんだなと初めて知りました。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbibr/2/1/2_jsbibr.2021.7/_html/-char/ja
若いマウスの腸内細菌を老齢個体に移植すると脳の機能が若返る
https://www.nature.com/articles/s43587-021-00100-z
魚(killifish)でも若い個体の糞を移植すると寿命が延びるようです
https://elifesciences.org/articles/27014
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
Somatic PIWI is important for cell differentiation in the regeneration.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124721012304?via%3Dihub
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01126-3 Green oxygen power plants in the brain rescue neuronal activity
Cancer resistance in specific rodents such as naked mole rat may be explained by genome rearrangement
https://www.nature.com/articles/s41514-021-00072-9
あれっ、いつの間にか翻訳の設定が「日→英」ではなくて、「英→日」になってる?
あと、Ctrl+Enterで送信にしていたはずが、いつの間にかEnterで送信になってた。。。最近LINE WORKSのサーバにトラブル発生したのかな。
僕は日→英です
うーん。。。
- Duminda Senevirathna
- https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01126-3 Green oxygen power plants in the brain rescue neuronal activity
https://twitter.com/Science_Release/status/1450091448653672450?t=Cr9rtM2E5yllqrn4z925nA&s=19
日本語の解説ツイートがありました。
https://twitter.com/Science_Release/status/1450091448653672450?t=Cr9rtM2E5yllqrn4z925nA&s=19
There was a Japanese commentary tweet.
- Shigeharu KINOSHITA
- カロリー制限が寿命を延ばすことは良く知られていますが、同じカロリーでもだらだら食べるのでなく、決まった時間に食べるようにすると寿命が延びるということが最近判ってきました。ショウジョウバエでそのメカニズムが明らかにされています。
related work in mouse
マウスに関連する作業
このマウスの実験は、カロリー制限しても、だらだら(少ないカロリーを)摂取すると寿命延長効果がなくなってしまうというもの。先のショウジョウバエの実験は、カロリー制限しなくても、決まった時間に(十分なカロリーを)摂取すると寿命延長効果があるというもの。これらは同じ現象なのか、違う現象なのか、興味深い。何にせよ、空腹の時間があるというのが大事のようですね。
The experiment on mice showed that even if calories are restricted, the effect of prolonging life will disappear if you consume too little calories.In the previous experiment with fruit flies, even if you don't limit calories, consuming enough calories at a certain time will prolong your life.It's interesting whether these are the same or different phenomena.Anyway, it seems important to have time for hunger.
NanoporeのQ20フローセル(99%以上の精度が出るフローセル)を申し込んだら、すぐに注文可能状態になりました。
If you apply for Nanopore's Q20 flow cell (flow cell with 99% accuracy or more), you will be ready to order immediately.
PacBioのHiFiは精度99.9%で20kbp程度読め、ナノポアのQ20フローセルは精度99%は出るようですね。あとはQ20フローセルで長さが100kbpとか読めるのか…でもこれまで当研究室で行ったナノポアだと10kbp程度しか読めないから、あまりアセンブル結果とかは変化ないかも?
私の行っているUMIでナノポアリードを補正する場合は、元のリードが汚いと補正しきれないので、99%の精度は楽しみです。
PacBio's HiFi can read about 20 kbp with 99.9% accuracy, and nanopore Q20 flow cells seem to have 99% accuracy.Also, can you read 100 kbp in Q20 flow cells?But with nanopores that I've done in this laboratory, I can only read about 10 kbp, so maybe the assembly results won't change much?
When correcting nanopore leads with my UMI, I can't correct them if the original leads are dirty, so I'm looking forward to 99% accuracy.
その精度本当に出るといいですね!
I really hope that accuracy comes out!
新しく出たR10.4限定らしいですね~。
It seems that the new R10.4 is limited~
This is cool. After designing hundreds of gRNAs and generating RNP complex libraries, they formed liquid droplets to encapsulate distinct RNPs with library barcodes. These droplets can visually be distinguishable and they could microinject a single droplet into each embryo, enabling multiplexed phenotype screening.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8870
かっこいいですね。 数百個のgRNAを設計し、RNP複合ライブラリを生成した後、ライブラリバーコードで個別のRNPをカプセル化するために液滴を形成した。 これらの液滴は視覚的に区別でき、それぞれの胚に1つの液滴を微小注入して多重表現型スクリーニングを可能にする。
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8870
マリンバイオテクノロジー学会の若手の会主催の秋のシンポジウムで、大阪大学の近藤滋先生の講演が行われます。学生の皆さんに刺激のある貴重な機会と思いますので、ぜひ参加してみてください。会員でなくても無料で参加できます。
https://drive.google.com/file/d/13CI9EhJS3n6R-RHn5WDr_Ua_sCQbvEpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxZBVYpEpNPXS5UA9SPLU70XDaimMw_M/view?usp=sharing
Shigeru Kondo of Osaka University will give a lecture at an autumn symposium sponsored by the Marine Biotechnology Society.I think it's an exciting and valuable opportunity for students, so please join us.You can participate for free even if you are not a member.
https://drive.google.com/file/d/13CI9EhJS3n6R-RHn5WDr_Ua_sCQbvEpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxZBVYpEpNPXS5UA9SPLU70XDaimMw_M/view?usp=sharing
Simple but smart way to compare DNA repair functions across short- and long-lived species
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj3284
短命種と長命種のDNA修復機能を比較するシンプルだがスマートな方法
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj3284
Domain-based homology search of Cas proteins revealed IS200/605 transposon family is the origin of CRISPR-Cas system. They performed in vitro cleveage assays and genome editing in HEK cell to show the putative ancestral proteins have RNA-guided DNA dsbreak activity.
Also it’s good to get rough sense for properly using DP based homology search like blast or probability model based search like HMMer
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj6856
CRISPR-Casシステムの起源はIS200605トランスポゾンファミリーであることが明らかになった。 彼らはHEK細胞で体外開裂検査とゲノム編集を行い、推定祖先タンパク質がRNA誘導DNAdsbreak活性を持っていることを示した。
また、BlastのようなDPベースの相同性検索やHMerのような確率モデルベースの検索を適切に使用するには、大まかに理解しておくとよいでしょう。
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj6856
More recently another paper talking about the same stuff came out, which is focusing on the application of these ancestral transposons for mammalian cells
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04058-1
つい最近、哺乳類細胞にこのような祖先のトランスポゾンを適用することに焦点を当てた同じことについて話す別の論文が発表されました。
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04058-1
Speciation in the deep: genomics and morphology reveal a new species of beaked whale Mesoplodon eueu
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1213
深部での種分化:ゲノム学と形態学は、ヒゲクジラメソポドンユーの新種を明らかにする
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1213
"big fish" :)
「ビッグフィッシュ」:)
長命種が多いメバル属ですね。これだけの数のde novoをやってるのがすごい。よく知られている寿命老化パスウェイ以外にもBTN遺伝子やCpGアイランドの変異など、魚の、あるいは非モデルグループの長命種のゲノムはやはり面白い
It's a genus of long-lived species.It's amazing that we're doing so many denovos.In addition to the well-known life-span pathways, the genome of long-lived species in fish or non-model groups, such as BTN genes and CpG Island variations, is still interesting.
san.. It's clear that Chromists do phagocytosis and endosymbiosis... https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488904002381#fig1 thank you.... this is also an interesting paper for endosymbiosis https://elifesciences.org/articles/58371
溝端秀彬 san.. クロミストが食細胞症と内共生をするのは明らかです。 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488904002381#fig1ありがとうございます。 これは内共生に関する興味深い論文でもある。https://elifesciences.org/articles/58371
Thank you so much!
The phonemenon you introduced about some layers of membrane is quite similar to the symbiosis of zooxanthellae.
That's why I am interested in that topic.
本当にありがとう!
いくつかの膜の層についてあなたが紹介したフォネメノンは動物園の共生と非常に似ています。
それが私がそのテーマに関心がある理由です。
phenomenon
現象
sensei, "In mammals, the Δ5 activity is allocated to the Fads1 gene, while Fads2 is a Δ6 desaturase. The loss of Fads1 in teleosts is a secondary episode, while the existence of Δ5 activities in the same group most likely occurred through independent mutations into Fads2 type genes." https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031950
木下茂治先生は「哺乳類ではΔ5活性はFads1遺伝子に割り当てられ、Fads2はΔ6デサチュラーゼである。 遠隔地でのFads1の喪失は二次的なエピソードであり、同じグループでのΔ5活性の存在は、Fads2型遺伝子への独立した突然変異によって起こる可能性が高い。」https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031950
- Duminda Senevirathna
@Shigeharu KINOSHITA sensei, "In mammals, the Δ5 activity is allocated to the Fads1 gene, while Fads2 is a Δ6 desaturase. The loss of Fads1 in teleosts is a secondary episode, while the existence of Δ5 activities in the same group most likely occurred through independent mutations into Fads2 type genes." https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031950
Thanks! Diversity in Fads function and FA compostion in vertebrates is interesitng.
ありがとう!ファッド機能の多様性と脊椎動物のFA堆肥化は必須です。
勉強になるしいいんじゃないでしょうか!
I think it's good to learn!
私も興味はありますが、メバルの論文は何でしょうか?
I'm also interested, but what is Meval's thesis?
- Naomi Hadisumarto
- 私も興味はありますが、メバルの論文は何でしょうか?
https://www.dropbox.com/s/c2pwbvjuz9tjncm/rockfish_genome.pdf?dl=0
- Shigeharu KINOSHITA
- https://www.dropbox.com/s/c2pwbvjuz9tjncm/rockfish_genome.pdf?dl=0
お手数をおかけ致しました、ありがとうございます
Thank you for the inconvenience.
皆さん
この論文の解読とともに、この規模の解析を行わないと高いレベルの論文にはならないことを認識させられました。もっとも進化的に珍しいものであれば単一ゲノムでもいいかもしれませんんが。
とりあえず月曜のセミナーの後に、進め方を相談しましょう。
またこれに加えて月1回ほど、有志者による、最新のシーケンス解読技術、データ解析技術、ハイレベルの論文などを検討したいと思いますが、いかがでしょうか?
ladies and gentlemen
Along with the decipherment of this paper, it was recognized that the paper would not be of a high level without this scale analysis.If it's the most evolutionarily rare, a single genome might do.
Anyway, let's discuss how to proceed after Monday's seminar.
In addition to this, I would like to consider the latest sequence decoding technology, data analysis technology, and high-level papers by volunteers about once a month. What do you think?
- Shigeharu KINOSHITA
- マリンバイオテクノロジー学会の若手の会主催の秋のシンポジウムで、大阪大学の近藤滋先生の講演が行われます。学生の皆さんに刺激のある貴重な機会と思いますので、ぜひ参加してみてください。会員でなくても無料で参加できます。
https://drive.google.com/file/d/13CI9EhJS3n6R-RHn5WDr_Ua_sCQbvEpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxZBVYpEpNPXS5UA9SPLU70XDaimMw_M/view?usp=sharing
リマインドですが、今週マリンバイオテクノロジー学会若手の会のシンポがあります。興味のある人は参加して下さい。
I would like to remind you that this week there will be a symposium for the Young Marine Biotechnology Society.If you are interested, please join us.
Sebastesのやつ僕は一通り読んだのでわからないことあったら聞いてください、何か役に立てるかもしれません
I've read all the Sebastes stuff, so if you don't understand anything, ask me, maybe I can help you.
そういえば、長い間ダウンしていたFishEnrichrが動くようになっていました。
https://maayanlab.cloud/FishEnrichr/
遺伝子名のリストからGene Ontologyだけ要約してくれるツールは多いのですけど、EnrichrはKEGGパスウェイなども対象にしてくれるので便利なツールです。
2年くらい前?にオープンになった当初から私はまだ一度も試すことが出来ていなかったのですが、同じ遺伝子名のリストを投げても、ヒト・マウスのDBであるEnrichrとは違うパスウェイが候補に挙がってきたので、魚類を研究している人はFishEnrichrのほうが良いのかもしれません。アコヤガイ、ヒラムシ、ウミウシなどはEnrichrの姉妹ツールでは何を使うのが良いかよくわかりませんが、イルカはとりあえず本家Enrichrで良いでしょうか。
Come to think of it, FishEnrichr, which had been down for a long time, started working.
https : // maayanlab . cloud / FishEnrichr /
There are many tools that summarize Gene Ontology from the genetic name list, but Enrichr is a convenient tool because it also targets KEGG pathways.
I haven't been able to try it since it first opened in ? two years ago, but even if I throw the same list of genetic names, FishEnrichr might be better for fish researchers because pathways are different from Enrichr, a human mouse DB.I'm not sure what to use with Enrichr's sister tools for red snails, flatworms, sea urchins, etc., but for now, is Enrichr the home of dolphins?
👍
Nuclear preservation in the cartilage of the Jehol dinosaur Caudipteryx https://www.nature.com/articles/s42003-021-02627-8
Jehol恐竜Caudipteryxの軟骨の核保存https://www.nature.com/articles/s42003-021-02627-8
https://kazumaxneo.hatenablog.com/entry/2021/12/20/092517
MOSGAという自動化アノテーションパイプラインがあるそうです。RNAseqを使ったトレーニングは出来なさそうだけど、とりあえず試すには良いかも?私もこれから使ってみます。
https://kazumaxneo.hatenablog.com/entry/2021/12/20/092517
There is an automated annotation pipeline called MOSGA.I don't think I can train with RNAseq, but maybe it's good to try it for now?I'll try using it from now on.
this paper was really interesting. single cell genomics is a powerful tool to study cell type emergences during evolution.
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)01329-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421013295%3Fshowall%3Dtrue
この論文は本当に興味深かったです。単細胞ゲノム学は進化中の細胞型緊急事態を研究する強力なツールです。
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)01329-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2フリーズ%2Fpii%2FS0092867421013295%3Fshowall%3真実
- Kijima Yusuke
- this paper was really interesting. single cell genomics is a powerful tool to study cell type emergences during evolution.
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)01329-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421013295%3Fshowall%3Dtrue
nicheな生物の面白い現象とその汎生物学的意義にいかに着目するか?その大切さに気づかせてくれますね
How do we focus on the interesting phenomena of niche organisms and their panbiological significance?It makes you realize how important it is.
全くおっしゃる通りです
You're absolutely right.
This work is really beautiful…
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.460388v1
この作品は本当に美しい…
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.460388v1
just found this paper but it looks important for us
https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(17)30229-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1934590917302291%3Fshowall%3Dtrue
ちょうどこの論文を見つけたところですが、木下茂治が劉光輝にとって重要に思えます。
https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(17)30229-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2フリーズ%2Fpii%2FS1934590917302291%3Fshowall%3真実
情報ありがとう。Currieらのグループの論文ですね。まだチェックしていませんでした。
Thank you for the information.It's a paper by Currie and his group.I haven't checked it yet.
まだチェックしてないですが同じオーサーのnature 2014も重要そうでした
I haven't checked it yet, but the same author's nature 2014 seemed important.
stratified hyperplasiaってアダルトでもがんがん起きてるんですね。出生後はmosaicだとおもってました
Stratified hyperplasia is happening even in adults.I thought it was mosaic after birth.
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
Very cool work from the Brunet lab
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.25.465616v1.full
Brunetラボのとてもクールな作品
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.25.465616v1.full
super simple but seems like a good method for isoform-level gene expression analysis and denovo transcriptome assay.
https://www.nature.com/articles/s41587-021-01136-7
非常に簡単ですが、アイソフォームレベルの遺伝子発現分析とデノボトランスクリプトームアッセイには良い方法のように思えます。
https://www.nature.com/articles/s41587-021-01136-7
super cool https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.12.476082v1
超クールhttps://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.12.476082v1
キーエンス蛍光顕微鏡を使っている皆さん
キーエンスの飯草さんから画像解析ソフトの無料体験版のお知らせです。
自分の解析で使えそうなら使ってみてください。
>お世話になっております。キーエンスの飯草です。
いつも【オールインワン蛍光顕微鏡】をご活用頂きまして、誠に有難うございます。
早速ですが、下記、〈解析アプリケーション(180日間)〉のURLをお知らせ致します。
※Windowのみの対応となります。
もしよろしければご使用方法について、ご紹介させて頂く事も可能です。
明日の午後も貴校にお伺いしておりますので、お気軽にお声がけ下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BZ-X800解析アプリケーション
無料体験版(180日)ダウンロードページのお知らせ
URL) https://www.keyence.co.jp/support/user/microscope/bz-x/soft/bz-x800.jsp
上記WEBページアクセス後、「BZ-X800ライセンスキー発行はこちら」というボタンを押すと、
お試し版発行コードを入力する画面に移りますので、以下のコードを入力してください。
発行コード:853761120
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~最新の<定量化事例>を、ご紹介させて頂きます~
※画面上をクリックすると、詳細をご覧頂けます。
糸球体(全体)における、マクロファージ定量解析
コロニーカウント計測
プレートスキャンと定量
タイムラプス解析
-----------------------------------------------------------------------------
株式会社キーエンス 飯草英明(いいぐさひであき)携帯:090-2041-5928
e-mail:iigusah@sales.keyence.co.jp
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館7F
TEL:03-5439-6755 FAX:03-5439-9466
------------------------------------------------------------------------------
Ladies and gentlemen, using the Keynes fluorescence microscope.
This is an announcement from Igusa of Keyence about the free trial version of the image analysis software.
If you think you can use it for your own analysis, please try it.
Thank you for your help.It's Keyens' rice grass.
Thank you very much for always using [All-in-One Fluorescent Microscope].
I would like to inform you of the URL of the parsing application (180 days) below.
※Only Window is supported.
If you don't mind, I can introduce you how to use it.
I will visit your school tomorrow afternoon, so please feel free to contact me.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BZ-X800 parsing application
Free trial (180 days) Download page notification
URL ) https://www.keyence.co.jp/support/user/microscope/bz-x/soft/bz-x800.jsp
After accessing the above Web page, press the "BZ-X800 License Key Issue here"
You will be taken to the screen where you enter the trial version issue code, so please enter the following code.
Issue code: 853761120
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~I would like to introduce the latest <quantification case>~
※Click on the screen to see the details.
macrophage quantitative analysis in glomerulus (whole body)
colony count measurement
plate scanning and quantification
time-lapse analysis
-----------------------------------------------------------------------------
Keyens Iigusa Hideaki Co., Ltd.Cellular: 090-2041-5928
e - mail : iigusah@sales.keyence.co.jp
7th floor of Shibaura 1-2-1 Sevance N Hall, Minato Ward, Tokyo, 105-0023
TEL : 03 - 5439 - 6755 FAX : 03 - 5439 - 9466
------------------------------------------------------------------------------
寿命研究では、象はなぜガンにならないか?というPetoのパラドックスがありますが、哺乳類全般に体サイズでガンのリスクは増大していないそうです(大きい動物はガンを抑制することができるようになったので体を大きくできた)。ただし、餌とガンのリスクには関係があり、
哺乳類を食べる哺乳類は、魚や無脊椎動物を食べる哺乳類や草食性哺乳類に比べてガンリスクが高くなります。
Why don't elephants develop cancer in life-span studies?There is a Peto paradox that says cancer risk is not increased in all mammals (big animals can now control cancer, so they can grow).However, it is related to food and cancer risk.
Mammals that eat mammals have a higher risk of cancer than mammals that eat fish and invertebrates and herbivores.
- 浅川修一
- On the origins and biosynthesis of tetrodotoxin
この論文とったか?あるなら送って
sciencedirectに東大のメールアドレスでユーザ登録してあれば、学外からでも普通にアクセス出来るようです。
https://geccutokyoacjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akyoshita_g_ecc_u-tokyo_ac_jp/EUhATFC8vvlCqo4LxYnmg5ABiWIDWQUz9hx-pWXr6nbWRg?e=8NpXzb
If you register as a user with the University of Tokyo email address in Sciencedirect, you can access it normally from outside the university.
https://geccutokyoacjp-my.sharepoint.com/ : b : / g / personal / akyoshita _ g _ ecc _ u - tokyo _ ac _ jp / EUhATFC 8 vvlCqo 4 LxYnmg 5 ABiWIDWQUz 9hx - pWXr 6 nbWRg ? e = 8 NpXzb
311室に戻りましたので、PDFでお送りいたしました。
I have returned to room 311, so I have sent it as a PDF.
https://research-er.jp/articles/view/107729
プレスリリースしか見てないですが、ギボシムシ興味深いです。
背骨がある動物(脊椎動物)では、万能細胞として知られる iPS 細胞(※1)は、数種類の因子を人為的に活性化することによってのみ得られるが、ギボシムシ(※2)は、その iPS 細胞を作り出すのに必要なリプログラミング因子(※3)を使って、再生していることを解明。
https://research-er.jp/articles/view/107729
I've only seen the press release, but it's interesting.
In animals with backbone (vertebrates), iPS cells known as pluripotent cells can only be obtained by artificially activating several factors, but the beetle (*2) uses reprogramming factors (*3) necessary to produce the iPS cells.
今、アースウォッチ・ジャパンというNPO主催の環境DNAを用いた魚類調査報告会を聞いていて、龍谷大の近藤先生が発表されているのですが、4月に世界初の環境DNAデータベースを公開と言ってます。私達も早く公開したほうが良いかもしれません。
I'm listening to a fish survey report using environmental DNA hosted by Earthwatch Japan, and Dr. Kondo of Ryutani University has announced that he will release the world's first environmental DNA database in April.It might be better for us to reveal it as soon as possible.
ボランティアは年間50人くらい、一人1地点1サンプルを送っているみたいでした。年々増やしていく計画とか。データ解析、DB開発を担当しているのは、メタゲノム解析ツールClaidentの作者の田邉晶史さんでした。5年前まで水産研究・教育機構にいた方です。やはりボランティアなどと連携して定期的に全国規模でやっていくという話になっていくものですね。
向こうのDB自体は見ていませんが、田邉さんはDB系は専門ではなさそうな印象があって、単にgoogle mapに組成をテキスト表示するピンを載せる程度かなと想像しています。こちらのDBのほうが作りは上だと思うので、なんとかこっちがメジャーになると良いですけど。
About 50 volunteers a year, each person seems to send one sample at a time.Like plans to increase year by year.The person in charge of data analysis and DB development was Akifumi Tanabe, the author of the meta-genome analysis tool Claident.I was at the Fisheries Research and Education Organization until five years ago.After all, it is said that they will do it regularly on a national scale in cooperation with volunteers.
I haven't seen the DB itself, but Mr. Tanabe has the impression that he doesn't specialize in DB, so I just put a pin on Google map to display the composition.I think this DB is better made, so I hope this becomes a major player somehow.
Cool work by Carl (a PI next to our lab at UBC). it’s surprising that MPRA (massively parallel reporter assay) and DL can predict the gene expression so accurately
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04506-6
カール(UBCのラボの隣にあるPI)の素晴らしい作品です。 MPRA(MassiveParallelReporterAssay)とDLが遺伝子発現をこれほど正確に予測できるのは驚きだ
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04506-6
- 浅川修一
- 吉武さん 即座やりましょう。中身は後でどんどん加えればいいんです
その後、既に公開はしておりまして、もうすぐ公式な公開宣言としてbioRxivに投稿できるかなというところです。あそこに投稿すると、比較的目新しいもの好きな人が数十人は見てくれる感じがします。
Since then, it has already been released, and I am wondering if I can post it on bioRxiv as an official public declaration soon.When I post there, I feel like dozens of people who like relatively new things will watch it.
そのように認識してもらえるように、twitterで公開を呟いたり、HPにLinkを張ったりしたいなと思っています(既に研究室のHPからはリンクを張っています)。
In order to be recognized like that, I would like to mutter the publication on Twitter and post a link on the website (I have already posted a link from the lab's website).
あと利用者のusability と他からデータをいれたもらう場合の提供のしやすさはとても大事と思います。そこが面倒だったり、分かりにくければ、逃げられてしまいます。近藤先生のは論文でてますか?
Also, I think it is very important that the user's usability and the ease with which it is provided when data is entered from others.If it's troublesome or difficult to understand, you'll be able to escape.Is Mr. Kondo's paper published?
論文どころか、まだ向こうは何も公開されていません。
Not to mention the paper, nothing has been disclosed over there yet.
たぶん、今日、明日には投稿すると思います。龍谷大のチームに届くように発信できると良いですよね。
I think I'll probably post it today or tomorrow.It would be nice if I could send it so that it could reach the Ryukoku University'
データ提供フォーマットもつくって公開しておいたらどうですか?初心者用と中上級者ようのフォーマットです。初心者用はGUIにしたらどうでしょう?こちらで設計し、見栄良い見せ方はWebデザイナーにアウトソーシングという手もあるかもしれません。
Why don't you make a data provision format and publish it?It's a format for beginners and intermediate-advanced users.Why don't you use the GUI?If you design it here and look good, you can outsource it to a web designer.
データ提供はSRAに登録してもらえれば良いです。個別はまだ考えておりません
You can register your data with the SRA.I haven't thought about it individually yet.
そうでした。SRA経由だと負担も少ないですね。例えば、大学や高校の生物部や民間b企業、地方の水産試験j等がNanopore で読んだあと、SRA登録までどうすればいいかの親切なマニュアル公開とかも準備しましょう。拡散研究会主催のWeb講習会を開い手みましょうか。
That's right. It's less burdensome via SRA.For example, prepare a kind manual on how to register SRA after reading it in Nanopore by the biology department of universities, high schools, private b companies, and local fisheries tests.Shall we hold a web workshop hosted by the Diffusion Study Group?
日本だったらDDBJへの登録が良いのでしょうけど、DDBJではなくSRAへの登録であればマニュアルを作れるかなと思います。DDBJへの登録は30サンプルを超えたあたりでDDBJのWEB登録システムがハングアップして必ず担当者にメール連絡するというのをマニュアルに入れるわけにもいかないですし。SRAなら英語でのわかりやすいマニュアルがあって、DDBJと違って簡単に登録できるので、説明する負担も少ないです。
中身でちょっと心配なのは、現在登録されているデータで沖縄の美ら海水族館の水槽が100件弱?ありそうですが、その水槽のデータに引っ張られて、「スマ」が割合として100%近くくるサンプルがあって、総合トップ2に来ているなどはちょっとどう表現すべきなのかなと思っているところではあります。
近藤先生たちはどう見せたいのか、という点では、
・どの地点でも良く見られる魚種ランキング
・たくさんの魚種が見られる地点ランキング
などの方向でデータをまとめていたので、現在トップページでパッと出てくるリッジグラフの順番は、もうちょっと意味を込めたほうが良さそうに思っています。
In Japan, it would be good to register with DDBJ, but if you register with SRA instead of DDBJ, I think you can make a manual.I can't include in the manual that DDBJ's web registration system locks up around 30 samples and always contacts the person in charge.SRA has an easy-to-understand manual in English, and unlike DDBJ, it is easy to register, so it is less burdensome to explain.
What I'm a little worried about is that there are less than 100 aquariums in Okinawa's Miraumi Aquarium based on the data currently registered?It seems likely, but I'm wondering how to express the fact that there are samples in which "smart" comes close to 100% due to the data in the aquarium, and that they're in the top two overall.
In terms of how Kondo teachers want to show it,
·Ranking of fish species that can be seen
·Place ranking where you can see many fish species
I was summarizing the data in the direction such as , so I think it would be better to put a little more meaning into the order of ridge graphs that suddenly appear on the front page.
先日の環境DNAを用いた魚類調査成果発表会の「Q&Aについて」が掲載されていました。一般の方の興味はこういう感じなのだろうと思います。
https://note.com/fugumaru/n/n3c3c252bfb2d
"The other day, ""About Q&A"" was published at the fish survey results presentation using environmental DNA."I think this is what the general public is interested in.
https://note.com/fugumaru/n/n3c3c252bfb2d
加齢による睡眠障害(眠りが浅い)はナルコレプシー(過眠症)の反対の現象が起きている
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh3021
Age-related sleep disorders (light sleep) are the opposite of narcolepsy.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh3021
吉武さん、研究室メンバー、学生諸君
Fuさんのマルチプレックスシーケンシングを行うのにどこのキットが低コストでできますか?イルミナ一択でしょうか?
イルミナなら純正はNextera, https://jp.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/apac/japan/documents/pdf/flyer-ye-campaign-dna-rna-lp-171208.pdf
ですが
NEBから安いキットが出ているようです。
https://www.nebj.jp/jp/info/2019_11_NEBNext_DNA_v1_brochure.pdf
https://www.nebj.jp/products/detail/2055
https://www.nebj.jp/products/detail/1976
などが使えそうですが、他に良いキットなどはありますでしょうか?
またMGIやその他?のプラットフォームでマルチプレックスシーケンシングに対応したキットなどありますでしょうか?
情報があればお知らせください。
Mr. Yoshitake, members of the laboratory, students,
Which kit can you do for Fu's multiplex sequencing at a low cost?Should I choose Illumina?
For Illumina, the genuine one is Nextera, https://jp.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/apac/japan/documents/pdf/flyer-ye-campaign-dna-rna-lp-171208.pdf
But...
There seems to be a cheap kit from NEB.
https://www.nebj.jp/jp/info/2019_11_NEBNext_DNA_v1_brochure.pdf
https://www.nebj.jp/products/detail/2055
https://www.nebj.jp/products/detail/1976
I think I can use and so on, but are there any other good kits?
Also, do you have a kit that supports multiplex sequencing on MGI and other platforms?
Please let me know if you have any information.
- 浅川修一
- 吉武さん、研究室メンバー、学生諸君
Fuさんのマルチプレックスシーケンシングを行うのにどこのキットが低コストでできますか?イルミナ一択でしょうか?
イルミナなら純正はNextera, https://jp.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/apac/japan/documents/pdf/flyer-ye-campaign-dna-rna-lp-171208.pdf
ですが
NEBから安いキットが出ているようです。
https://www.nebj.jp/jp/info/2019_11_NEBNext_DNA_v1_brochure.pdf
https://www.nebj.jp/products/detail/2055
https://www.nebj.jp/products/detail/1976
などが使えそうですが、他に良いキットなどはありますでしょうか?
またMGIやその他?のプラットフォームでマルチプレックスシーケンシングに対応したキットなどありますでしょうか?
情報があればお知らせください。
在庫状況を把握しておりませんが、200サンプルくらいであれば研究室にあるswiftのキットがまだ残っていると思います。シイタケ用に100サンプルほど使用する予定ですが、半分量で使えば400サンプル分購入してあるので、十分余っているはずです。溝端くんが知っていると思います。
I don't know the stock status, but I think I still have the Swift kit in the laboratory if it's about 200 samples.I'm planning to use about 100 samples for shiitake mushrooms, but if I use half the amount, I bought 400 samples, so there should be enough left over.I think Mizubata-kun knows.
ちなみに、一倍体シイタケのDNAライブラリー調整は難航しておりまして、DNAの濃度が薄いため普通にDNAライブラリー調整を行っても数サンプルしかできそうにありませんでした。そこで全ゲノム増幅キットを使ったのですが、特定のDNA抽出キットで抽出されたDNAしか増幅することが出来ておらず、20サンプル程度しか準備できそうにない状況です。簡単には上手くいきそうにないので、黒河内さんのほうでもDNA抽出・ライブラリー調整方法を検討して頂きたいと相談しております。
By the way, adjusting the DNA library of the polyploid shiitake mushroom was difficult, and the DNA concentration was low, so even if I adjusted the DNA library normally, I could only do a few samples.So I used the whole genome amplification kit, but only DNA extracted from a specific DNA extraction kit can be amplified, so I think I can only prepare about 20 samples.Since it doesn't seem to work easily, Kurokawauchi would like you to consider DNA extraction and library adjustment methods.
swiftは確か最低でも数ngは必要だった気がしますので、NEBのほうがカタログ通りであれば適していると思われます。今すぐ購入できるのでしょうか?
I think I needed at least a few ng of swift, so I think NEB would be more appropriate if it follows the catalog.Can I buy it now?
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
RNA extraction free bulk RNA-seq method. 500 USD per 200 samples
https://genomebiology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13059-022-02660-8.pdf
RNA抽出遊離バルクRNA-seq法。 サンプル200個あたり500USD
https://biology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13059-022-02660-8.pdf
looks decent
見栄えが
Cryptic and abundant marine viruses at the evolutionary origins of Earth’s RNA virome https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm5847
地球のRNAウイルスの進化的起源における暗号化された豊富な海洋ウイルスhttps://www.science.org/doi/10.1126/science.abm5847
Today’s nature. Here they performed large scale whole genome sequencing for 16 mammalian species and found a clear correlation between their lifespan and somatic mutation rates. now I wonder if fish has a similar trend because I’ve seen relaxation of negative selection on DNA repair genes in zebrafish and the previous rockfish paper was also talking about evolved DNA repair machinery in long-lived species
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04618-z
今日の自然。 ここで彼らは16種の哺乳類に対して大規模な全ゲノム配列決定を行い、その寿命と体細胞突然変異率の間に明確な相関関係を発見した。 私もゼブラフィッシュのDNA修復遺伝子に対する否定的な選択の緩和を見たことがあるし、以前の岩魚論文も長寿種の進化したDNA修復機械について話していたから、魚も同じような傾向があるのだろうか。
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04618-z
Unlike cephalopods, vertebrate eyes have an "inverted" retina network. But, according to a recent article on Current Biology, this awkward design might be reasonable in the view of eye evolution.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982222003359?dgcid=author
頭足類とは異なり、脊椎動物の目は「反転した」網膜網を持っています。 しかし最近のCurrentBiologyの記事によると、このぎこちないデザインは目の進化の観点から合理的かもしれません。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982222003359?dgcid=author
山中因子によるiPS細胞化は一種の若返りといえますが、幹細胞化してしまうので元の細胞の性質はなくなってしまいます。筆者らはDox発現系を利用して山中因子を短時間限定的に発現させることで、幹細胞化することなく、若返りだけさせることに成功しました。実験では中年の皮膚細胞が30歳若返ったそうです。
https://elifesciences.org/articles/71624
iPS cellization by Yamanaka factor is a kind of rejuvenation, but since it becomes a stem cell, the original cell's properties disappear.By using the Dox expression system to express Yamanaka factors for a short time, we succeeded in rejuvenating them without stem cellization.According to the experiment, middle-aged skin cells are 30 years younger.
https://elifesciences.org/articles/71624
面白いですね。逆にめちゃくちゃOSKMを過剰発現させるとvivoでtotipotent(全能性)の腫瘍を誘導できるらしくて、割とdosage dependentで表現系変わるのも興味深いです
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25249-4
It's interesting. On the other hand, if you overexpress OSKM, you can induce totipotent tumors in vivo, and it's also interesting to see how the expression changes with a relatively dose dependent.
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25249-4
あと昨日のNatureにめちゃくちゃSTAPなのが出ててラボで盛り上がりました
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04593-5
And yesterday's Nature had a really STAP, and it was exciting in the lab.
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04593-5
これがほんとなら、山中因子同様に、薬剤処理の濃度や時間を変えることで細胞の若返りだけ起こすこともできるのかな。これぞ若返りの薬?
If this is true, like the Yamanaka factor, it is possible to only rejuvenate cells by changing the concentration and time of drug treatment.Is this the medicine for rejuvenation?
- Kijima Yusuke
- Today’s nature. Here they performed large scale whole genome sequencing for 16 mammalian species and found a clear correlation between their lifespan and somatic mutation rates. now I wonder if fish has a similar trend because I’ve seen relaxation of negative selection on DNA repair genes in zebrafish and the previous rockfish paper was also talking about evolved DNA repair machinery in long-lived species
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04618-z
同一の幹細胞由来の細胞群であるintestinal cryptをLMDで切除してゲノムシーケンスすることで体細胞の変異率を算出するという手法が面白い。ここで調べている哺乳類の場合、寿命の多様性がせいぜい数十倍だけど、魚は数百倍~1000倍にもなる。魚もこの寿命と体細胞変異率の逆相関に乗るのなら、数百年の寿命の魚種はむちゃくちゃ体細胞変異率が低いんだろうか?また、それはどのようなメカニズムになっているんだろう?
An interesting method is to calculate the rate of variation of somatic cells by performing genome sequencing by excision of the testinal crypto which is a group of cells derived from the same stem cell with LMD.In the case of mammals examined here, life expectancy is at most several tens of times higher, but fish are hundreds to 1,000 times higher.If fish also ride the inverse correlation between life expectancy and somatic cell mutation rate, do fish species with a life span of several hundred years have extremely low somatic cell mutation rates?Also, what kind of mechanism is it?
https://mainichi.jp/articles/20220422/k00/00m/040/101000c
日本でもウミウシの飼育成功してるんですね
https://mainichi.jp/articles/20220422/k00/00m/040/101000c
Sea urchin breeding is successful in Japan, isn't it?
西田さんはムカデミノウミウシの継代飼育について以前お話しされていましたが、センジュミノウミウシでも成功したんですね!興味深いです、ありがとうございます。
Mr. Nishida talked about the successive breeding of centipede sea slugs before, but he also succeeded in raising them!It's interesting, thank you.
super interesting
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04641-0
basically they found a new form of skin cell division without DNA replication during zebrafish development. such cell clones are frequently observed at rapidly growing stages, which means this is utilized to cover the body surface to quickly respond to the growth
基本的にゼブラフィッシュの開発中にDNA複製のない新しい形態の皮膚細胞分裂を発見した。 このような細胞クローンは急速に成長する段階で頻繁に観察されるが、これは成長に迅速に対応するために体表面を覆うために利用されることを意味する
- 浅川修一
- https://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-0028-874E-8/Dissertation%20Steffen%20Kawelke.pdf?sequence=1
Thank you sensei
ありがとう先生
↑DNBを用いた高解像度spatial transcriptome
↑ High resolution spatial transcriptome using DNB
https://www.digital-biology.co.jp/allianced/learning/5-19-pacbio-dovetail-denovo-webinar/
私はサンプリングに向かってしまうので聞けないのですが、『PacBio社の高精度ロングリード と Dovetail Genomics社の近接ライゲーションを用いたデノボゲノムアセンブリ』というタイトルでウェビナーがあるみたいです
https://www.digital-biology.co.jp/allianced/learning/5-19-pacbio-dovetail-denovo-webinar/
I can't ask because I'm heading for sampling, but it seems like there's a webinar titled "Denovo Genom Assembly with PacBio's High Accuracy Long Reed and Dovetail Genomics' Proximity Ligations."
ちなみに明日です
By the way, it's tomorrow.
News の方で紹介した論文で、4万のヒトトランスクリプトームのデータ解析¥のデータを我々で再解析して、ユビキタスで発現量の多い遺伝子のリストを作ったところ、無茶苦茶順当な結果が出ました。そのリストを発現量の多い方から掲示します。
In the paper introduced by News, we re-analyzed the data analysis の of 40,000 human transcriptomes and made a list of ubiquitous and expressive genes, and we found that the results were absurd.The list will be posted from the person with the most expression.
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/06/press20220602-01-anemone.html
東北大からeDNAのDBが公開されたみたいですね。
登録しないと使えなさそうでしたが、DBのリンクも以下に示します。
https://db.anemone.bio/
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/06/press20220602-01-anemone.html
It seems that the DB of eDNA has been released from Tohoku University.
I couldn't use it without registering, but the DB link is also shown below.
https://db.anemone.bio/
日本郵船など企業も協力してサンプルを取得しているようです
It seems that companies such as Nippon Yusen are also cooperating to obtain samples.
ありがとうございます!以前シンポジウムで予告されていたDBですね。ログインしてみた感じ、MitoSearchと比べるととても使いづらい感じがしましたが、、、FASTQデータがダウンロード出来るので、内部用のMitoSearchにはデータを追加してどうなるか見てみるのは楽しそうだなと思いました。座標情報も大体ついているようですし。
Thank you!This is the DB that was previously announced at the symposium.When I logged in, I found it very difficult to use compared to MitoSearch, but since FASTQ data can be downloaded, I thought it would be fun to add data to the internal MitoSearch and see what happens.It seems to have coordinate information.
一部、確認が必要なところがあると思いますが、ヒトは高等動物ゲノム解析の先行モデルなので概要を理解しておいてください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbibr/3/1/3_jsbibr.2022.primer2/_html/-char/ja?fbclid=IwAR0OR_XfXc35gVD4L8pvL84ig1zFgQgd5lMoycjOd2x-OtgVEv-qdTFFq6Y
There may be some things that need to be confirmed, but humans are the leading models of higher animal genome analysis, so please understand the outline.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbibr/3/1/3_jsbibr.2022.primer2/_html/-char/ja?fbclid=IwAR0OR_XfXc35gVD4L8pvL84ig1zFgQgd5lMoycjOd2x-OtgVEv-qdTFFq6Y
紹介されている用いられた技術の中で「10XのStrand-seq」とあるのは恐らく誤りで、10xのLinked-readと、体細胞組み換えを利用して連鎖解析のようなことが可能となるStrand-seqも使ったということだったと思います。Strand-seqは恐らく今マイクロ流路を使って簡便にシーケンスすることは出来ていないはずで、元の論文の中でも使ったとだけは書かれているけど、実際のデータは出てこなかったように思います。(誰か精読した方がいたら教えてください。。。)
"Among the techniques introduced, ""10X Strand-seq"" was probably wrong, and I think they also used 10x Linked-read and Strand-seq, which allows for chain analysis using somatic cell recombination."Strand-seq is probably not easily sequenced using microflow channels now, and although it is written that it was used in the original paper, the actual data did not appear.(Please let me know if anyone has read carefully...)
カロリー制限には寿命延長効果がありますが、その効果は、
少しずつ一日中食べる<<活動時間は空腹で休息時間に食べる<<活動時間に食べて休息時間は空腹
休息時間(ヒトの場合は日暮れから朝まで)に空腹を感じることが大事だそうです。
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0297
Calorie restriction has the effect of prolonging life, but the effect is:
Eat little by little all day <<Eating during activity time is hungry and eating during rest time <<Eating during activity time is hungry during rest time
It is said that it is important to feel hungry during rest time (from sunset to morning in the case of humans).
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0297
夜ごはんを抜くのは、朝や昼よりも個人的に辛いですが、夜を抜くと効果的なのですね。
It's personally harder to skip dinner than in the morning or in the afternoon, but it's effective to skip dinner.
「少なくとも12時間の絶食+活動時間(ヒトの場合日中)に少なめの食事」、というのが一番寿命延長効果があった(好きなだけ食べるグループより35%寿命延長)そうです
"At least 12 hours of fasting + eating less during activity (in humans, during the day)" was the most effective way to prolong life (35% longer than in groups where people eat as much as they want).
誰かそれを実践してみて欲しいですね。数年ならともかく、一生となると私はやりたくない、、、、
I want someone to try it.I don't want to do it for the rest of my life, let alone for a few years...
ちょっとゆるくなってるけど、16時間絶食をやってる(しばらくやっていた)。いま一部流行ってるよ。夜8時までにたべて、昼まで食べなければ、できないことはない。16時間中空腹ならばナッツ系をたべる。
It's getting a little loose, but I've been fasting for 16 hours (I've been doing it for a while).Some of them are in fashion now.If you don't eat by eight o'clock in the evening and don't eat until noon, there'If you're hungry for 16 hours, eat nuts.
human HSC subpopulation with high stemness and quiescence expresses GPRC5C, which interacts with hyaluronic acid
https://www.nature.com/articles/s41556-022-00931-x
高い茎性と停止性を持つヒトHSC亜集団は、ヒアルロン酸と相互作用するGPRC5Cを発現する
https://www.nature.com/articles/s41556-022-00931-x
Illumina is planning to release Nextseq PE300 this year. Great news for amplicon seq users
https://emea.illumina.com/company/news-center/press-releases/press-release-details.html?newsid=ba2ff00d-19fb-4080-8c2d-4798685055f0
Illuminaは今年、NextseqPE300を発売する予定です。 ampliconseqユーザーにとっての朗報
https://emea.illumina.com/company/news-center/press-releases/press-release-details.html?newsid=ba2ff00d-19fb-4080-8c2d-4798685055f0
上位機種でも長く読めるようにしてほしいですよね。あとPE500くらいまで読めるようにならないかとか。
I want you to be able to read even the top models for a long time.Also, I wonder if I can read up to PE500.
亀は年を取らない?
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7811
Don't turtles age?
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7811
マイクロ流路?を用いたeDNAの抽出方法
Sterivex法で使用されるろ過容量の1 / 20〜1 / 40で済み、従来法で抽出されたDNAの濃度と同様な結果が得られたそうです。ステップが簡略化されることで、サンプルの汚染リスクの軽減が期待できるそうです。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.13657
EXTRACTION METHOD OF EDNA USING MICRO FLOW PASSAGE?
The filtration capacity used by the Sterivex method was 1/20 to 1/40th, and the concentration of DNA extracted by the conventional method was similar results were obtained.By simplifying the steps, you can expect to reduce the contamination risk of the sample.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.13657
- Ryo Yonezawa
- マイクロ流路?を用いたeDNAの抽出方法
Sterivex法で使用されるろ過容量の1 / 20〜1 / 40で済み、従来法で抽出されたDNAの濃度と同様な結果が得られたそうです。ステップが簡略化されることで、サンプルの汚染リスクの軽減が期待できるそうです。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.13657
シリンジで押してろ過&DNA抽出が3分でできると楽で良いですね。DNA溶出にカラムの素材か磁気ビーズを使うように改良してくれて、1枚100円くらいで売ってくれる日が来ないかな。
It would be easier and better if it can be filtered and DNA extracted in 3 minutes by pressing it with a syringe.I wonder if the day will come when they will improve the use of column materials or magnetic beads for DNA elution and sell them for about 100 yen each.
- Kazutoshi Yoshitake
- シリンジで押してろ過&DNA抽出が3分でできると楽で良いですね。DNA溶出にカラムの素材か磁気ビーズを使うように改良してくれて、1枚100円くらいで売ってくれる日が来ないかな。
ですね。 ラボのアスピだと一日で大量に濾過するのは大変ですからね…
流路の型ができてしまえば、安く済みそうですがステリべクスの価格から考えると販売されたとしてもいい値段しそうですね…
Well, it's hard to filter out a lot in one day with a lab aspirin...
Once the channel model is made, it will be cheaper, but considering the price of the stereo, it would be a good price even if it were sold...
木下先生と吉田くんに共有を頼まれたので、ここで共有いたします。
NADを加えたら神経筋が改善された
https://skeletalmusclejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13395-019-0206-1
NAD interconnects with cation exchanger and circadian rhythm
https://www.life-science-alliance.org/content/5/9/e202101194
Dr. Kinoshita and Mr. Yoshida asked me to share it, so I will share it here.
The addition of NAD improved the neuromuscular muscles.
https://skeletalmusclejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13395-019-0206-1
NAD interconnects with country exchange and circadian rhythm
https://www.life-science-alliance.org/content/5/9/e202101194
- Naomi Hadisumarto
- 木下先生と吉田くんに共有を頼まれたので、ここで共有いたします。
NADを加えたら神経筋が改善された
https://skeletalmusclejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13395-019-0206-1
NAD interconnects with cation exchanger and circadian rhythm
https://www.life-science-alliance.org/content/5/9/e202101194
ありがとうございます
Thank you.
- 浅川修一
- https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09F8XX381/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
ありがとうございます
Thank you.
https://research-er.jp/articles/view/112492
キリフィッシュでクリスパーの実験系が確立されたみたいですね
https://research-er.jp/articles/view/112492
I think the Christopher experiment system was established in Kirifish.
キリフィッシュでのゲノム編集は以前からやられており、
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415001166
複数のgRNAを同時に使うことで第一世代で表現型を解析するというのも以前からありますが、
両方組み合わせたというところがポイントなのかな。3種類のgRNA/1遺伝子でほぼ100%というのは、どんな遺伝子に対してもそうなのか?など気になります。
Genome editing in Kirifish has been done for a long time.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415001166
It has been a long time since we analyzed phenotypes in the first generation by using multiple gRNAs at the same time.
I guess the point is that they are combined.Is almost 100% of the three gRNA/1 genes for any gene?and so on.
キリフィッシュでやったってのがポイントなんだと思います。石谷先生とこないだミーティングさせてもらったんですが、キリフィッシュ飼い始めて初めての論文みたいです
I think the point is that we did it with Kirifish.I had a meeting with Dr. Ishitani the other day, and it seems like it's my first paper since I started keeping a giraffe fish.
みたいですし
I think so.
キリフィッシュのバイオリソースが日本で立ち上がれば、ぜひ利用したいです
I would love to use Kirifish's bio-resources once they are launched in Japan."
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0571
A concise synthesis of tetrodotoxin
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0571
テトロドトキシンの簡潔な合成
Pfamのウェブサイトがクローズするようです。データの更新を止めるわけではないようですが。
https://twitter.com/pfamdb/status/1555149527228813314?s=21&t=Cd0rGVZnjdrmcXeTNQ9L0g
The Pfam website seems to be closed.It doesn't seem to stop updating the data.
https://twitter.com/pfamdb/status/1555149527228813314?s=21&t=Cd0rGVZnjdrmcXeTNQ9L0g
極地域の深海にいるニシオンデンザメがベリーズの沖でも見つかったそうです。
https://www.cnn.co.jp/fringe/35191260.html
It is said that a python shark in the deep sea of the polar region was also found off Belize.
https://www.cnn.co.jp/fringe/35191260.html
I saw this too and was so surprised! I had no idea their distribution was so widespread. They found it near a famous atoll in Belize so I guess maybe they can be present even in equatorial waters if there is some kind of reef/atoll ecosystem they can feed from below. I wonder how many are there around the atoll..
私もこれを見てびっくりしました。 こんなに普及しているとは知りませんでした。 ベリーズの有名な環礁の近くで発見されたので、もし下から餌を食べさせてくれるような珊瑚礁や環礁の生態系があれば、赤道の海にも存在できるかもしれません。 環礁の周りには何人いるのでしょうか。
- Andre Lanza
- I saw this too and was so surprised! I had no idea their distribution was so widespread. They found it near a famous atoll in Belize so I guess maybe they can be present even in equatorial waters if there is some kind of reef/atoll ecosystem they can feed from below. I wonder how many are there around the atoll..
ベリーズ、良いところですね。今研究に使っているニシオンデンザメはノルウェー沖でサンプリングしましたが、ベリーズに行ってサンプリングしたいです。
Belize, that's a good place.I sampled the python shark that I am currently using for my research off the coast of Norway, but I would like to go to Belize and sample it.
DNAイベントレコーディングに関する簡単なレビューがうちのラボから出てます(僕は書いてません)。興味がある方はどうぞ
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo3471
A brief review of DNA event recording is coming from our lab (I didn't write it down).If you're interested, go ahead.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo3471
老化がなぜ誕生したかについての進化的考察。老化しない(かもしれない)種についても議論されています。https://note.com/masakadokawata/n/n4ac4f475d0fa
Evolutionary consideration of why aging was created. Species that do not (may) age are also discussed.https://note.com/masakadokawata/n/n4ac4f475d0fa
scRNA sequencing of a cell without killing it
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05046-9
細胞を殺さずに細胞をscRNA配列決定する
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05046-9
This is interesting. Early oocytes are known to be highly dormant yet metabolically active, and they found the extreme dormancy is derived from the loss of mitochondrial complex 1, leading to low ROS production.
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04979-5
これは面白いですね。 初期の卵母細胞は休眠性が高いが、代謝的に活性化されることが知られており、極端な休眠性はミトコンドリア複合体1の損失から派生し、低ROS生産につながることが分かった。
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04979-5
不死の生物のゲノム解析
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2118763119
genome analysis of immortal organisms
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2118763119
ベニクラゲのゲノム解析が出てしまいましたね
beauty of Shimomura
So we've got a genome analysis of the jellyfish.
- Shigeharu KINOSHITA
@下村美秀
ベニクラゲのゲノム解析が出てしまいましたね
翻訳サイトにかけてですが、結果等読んでみました…若返りする、しないベニクラゲの2種を比べて発現の異なる点やアノテーションをつけて候補をとにかく絞った上で、こんなに細かくそれぞれの遺伝子がコピー数がどうだ、他の生物と塩基が違う事での結合性の変化など調べてあって…
遺伝子の知識が乏しい自分なのでとにかく凄いと思いました…
DNAの安定性や修復性に関わる多くの点でゲノム改変しないと他の生物に応用出来ない気もしました。
I went to the translation site, and I read the results, etc. ... I compared two species of rejuvenating, non-rejuvenating, non-rejuvenating, annotated and narrowed down the candidates, and looked at how many copies each gene has and how many bases it has.
I thought it was just amazing because I don't know much about genes.
In many respects, DNA stability and repairability, I felt that I had to modify the genome to apply it to other organisms.
- Kijima Yusuke
@Ryo Yonezawa https://www.nature.com/articles/s41598-022-19355-6
ありがとうございます。まだ見てなかったので助かります。
明後日、動物学会でこのグループの発表があるので色々と聞いてこようかと思ってます。
Thank you.I haven't seen it yet, so it's helpful.
The day after tomorrow, there will be an announcement of this group at the Zoological Society, so I'm thinking of asking a lot of questions.
下村くん 国内のベニクラゲの先生と話をして、どうなったんでしたっけ?何れにせよ、ゲノムのデータが使えれば使わしてもらえばいいですし、変態するときに何が起きるのか、調べやすくなると思います。
Mihide Shimomura, what happened when I talked to a teacher of Japanese jellyfish?Anyway, if you can use the genomic data, you can use it, and I think it will be easier to find out what happens during transformation.
- 浅川修一
@下村美秀 下村くん 国内のベニクラゲの先生と話をして、どうなったんでしたっけ?何れにせよ、ゲノムのデータが使えれば使わしてもらえばいいですし、変態するときに何が起きるのか、調べやすくなると思います。
前回聞いた時、今飼育している東京電気大学の先生から9月初め頃になったら増えてるかもしれないのでもう一度聞いてくれないかとの事でして、まだもう一度聞いてませんでした。ゲノムデータについては継代飼育を引き継いでいた前の方から若返りする種である事は同定済とは言われてますが、どの程度のデータがあって使わせて貰えるかは聞いてません。
The last time I heard it, a teacher at Tokyo Electric University, who is raising it now, asked me to ask again because it might increase around the beginning of September, so I haven't heard it yet.As for genomic data, it is said that it has been identified as a rejuvenating species from the previous person who took over the breeding process, but I have not heard how much data I can use.
データは論文がパブリッシュされていれば誰でも使えるはず。共同研究として話をすすめたいと思うけど、「東京電気大学の先生」「継代飼育を引き継いでいた前の方」がどういう関係で誰なのか、よくわかりません。
The data should be available to anyone as long as the paper is published.I'd like to recommend this as a joint study, but I don't know exactly what kind of relationship the "teacher of Tokyo Electric University" and the "former person who took over the breeding of the next generation" are and who they are.
https://bioone.org/journals/zoological-science/volume-33/issue-4/zs150186/De-Novo-Assembly-of-the-Transcriptome-of-Turritopsis-a-Jellyfish/10.2108/zs150186.full
がすでに出ているね。 違った切り口として、相同染色体の多型の数や若返り前後の変異率などを調べてみるのもどうだろう?
Wikiをみると久保田先生は10回若返らせているから、もしDNAがのこっているなら、比べてみるのもいいと思うけど。
https://bioone.org/journals/zoological-science/volume-33/issue-4/zs150186/De-Novo-Assembly-of-the-Transcriptome-of-Turritopsis-a-Jellyfish/10.2108/zs150186.full
There's already been . How about looking at the number of polymorphisms in homologous chromosomes and the rate of variation before and after rejuvenation?
Looking at the wiki, Mr. Kubota has been rejuvenated 10 times, so if DNA remains, it would be good to compare it.
A regulatory network of Sox and Six transcription factors initiate a cell fate transformation during hearing regeneration in adult zebrafish https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666979X22001124
SoxとSixの転写因子の規制ネットワークは、成体ゼブラフィッシュの聴覚再生中に細胞運命の変化を引き起こすhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666979X22001124
I used the 12S GoFish nested PCR protocol to isolate dolphin eDNA from Nagasaki samples... the protocol is here https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198717
12SGoFishネストPCRプロトコルを使用して、長崎のサンプルからイルカのDNAを分離しました。 プロトコルはこちらhttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198717
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
Evolution of the ancestral mammalian karyotype and syntenic regions
https://doi.org/10.1073/pnas.2209139119
哺乳類の核型と合成領域の進化
https://doi.org/10.1073/pnas.2209139119
T cells elongate telomere by getting extracellular vesicles containing telomere fragments and rad51 recombination factor from antigen prerenting cells. kind of crazy stuff…
https://www.nature.com/articles/s41556-022-00991-z
T細胞はテロメア断片とrad51再結合因子を含む細胞外小胞を抗原プレレンティング細胞から得ることによってテロメアを伸長させる。一種のクレイジーなもの…
https://www.nature.com/articles/s41556-022-00991-z
PacBioはsequelの次にRevioという機種を出すっぽいです。価格が1/15になるとか。ナノポアの精度が上がって、今後はナノポアかと思ったけど、やっぱりPacBioという時代が続くかも?
It seems that PacBio will release Revio after sequel.The price will be 1/15th.The accuracy of the nano-pore has improved, so I thought it would be a nano-pore in the future, but maybe the era of PacBio will continue?
Single-cell genomics without any special equipment such as microfluidics.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.06.10.495582v1.full
マイクロ流体学のような特別な装置なしの単一細胞ゲノミクス。
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.06.10.495582v1.full
これ谷内江研が五年前くらいまで取り組んでてポシャったアイデアで、うまく行ったことに古株の人たちは驚いてました(余談)
This was an idea that Taniuchi Eken had been working on until about five years ago, and people in old stocks were surprised that it worked out well.
同時期に出たこれも面白かった
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.01.498266v1.full.pdf
It came out at the same time and it was fun.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.01.498266v1.full.pdf
PD-1やPD-L1はガン細胞の増殖に関わっていて、これらの阻害剤は免疫チェックポイント阻害剤としてガン治療に用いられていますが、同じ仕組みが老化細胞の増殖でも働いていて、免疫チェックポイント阻害剤は若返りにも効いた、という話。寿命とガン耐性は密接に関わっているので、その点からも興味深い。
PD-1 and PD-L1 are involved in cancer cell proliferation, and these inhibitors are used in cancer treatment as immune checkpoint inhibitors, but the same mechanism works in aging cell proliferation, which is also interesting because life and cancer resistance are closely related.
Speciation and phenotypic diversification are driven by fixed genetic mutations in the classic theory, but this report suggests epigenetic and transcriptional remodeling happen prior to genetic mutations (less riskier?). Interesting
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01894-w
種分化と表現型多様化は古典理論の固定遺伝子突然変異によって推進されるが、今回の報告書は遺伝子突然変異以前にエピジェネティックと転写リモデリングが発生することを示唆する(危険性が低い?)。 面白い
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01894-w
and yet another cool stuff on the same journal talking about the gene evolvability depending on the importance of the belonging regulatory circuits (the conclusion was that genes are more evolvable than believed before, even if a gene has a central role in a deeply conserved circuit)
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01906-9
また、同じジャーナルに掲載されているもう1つのクールな記事では、遺伝子の進化可能性について、所属する調節回路の重要性に応じて論じている(結論は、遺伝子が深く保存された回路において中心的な役割を持っていても、遺伝子は以前に考えられていたよりも進化しやすいということだった)。
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01906-9
ついにアコヤガイゲノムver4が出ましたね。
https://marinegenomics.oist.jp/pearl_4_1A/viewer/info?project_id=110
https://marinegenomics.oist.jp/pearl_4_1B/viewer/info?project_id=111
ハプロタイプ別に2つのゲノムが公開されたみたいですね。
Finally, the red mussel genome ver4 came out.
https://marinegenomics.oist.jp/pearl_4_1A/viewer/info?project_id=110
https://marinegenomics.oist.jp/pearl_4_1B/viewer/info?project_id=111
It seems that two genomes were released for each haplotype.
白色化の候補領域について軽く比較してみました。
v4と同時に、pfu v3のゲノムもようやく正式版が公開されていましたが、以前OISTから送って頂いた旧v3ゲノムと比べると、ゲノム配列自体はたぶん同じもののようですが、遺伝子アノテーションが違うようでした。
使われた技術としては、
v3: 昔のPacBio RSII+HiC
v4: PaCBio HiFi+HiC
かなと思います。
さて、候補の一つのg26480遺伝子のゲノム配列自体はそんなに変わっていないようですが、その前後ではそれなりにゲノムの差異がありそうでした。v3は短いscaffoldを無理やりHi-Cで伸ばした印象がありましたが、やはり細かい間違いが多かったのだなと思いました。
I made a light comparison of the candidate areas for whitening.
At the same time as v4, the pfu v3 genome was finally released, but compared to the old v3 genome that OIST sent me before, the genome sequence itself seemed to be the same, but the gene annotation seemed to be different.
The technology used was:
v3—Old PacBio RSII+HiC
v4 —PaCBio HiFi+HiC
I think so.
Now, the genome sequence of one of the candidates, the g26480 gene itself, doesn't seem to have changed that much, but before and after that, there seemed to be some differences in the genome differences.I had the impression that v3 forced the short scaffold to grow with Hi-C, but I thought there were many minor mistakes.
こういうのってrnaseqで遺伝子予測のクオリティあげてもこんなにミスってるもんなんでしょうか?
Is there such a mistake in raising the quality of gene prediction with rnaseq?
もとのv3ゲノムがぐちゃぐちゃだったので、このくらいは違うだろうと思っていたというのもありますが、そもそも遺伝子予測自体の精度がそんなに高くないはずなので、こんなものではないでしょうか。
論文で遺伝子予測に使われているAugustusも10年以上前からあるプログラムですしね。そろそろDeepLearningを使った高精度の遺伝子予測プログラムとか出てくると話は違うかもしれませんが。
The original v3 genome was messy, so I thought it would be this different, but the accuracy of gene prediction itself shouldn't be that high, so I think it's like this.
Augustus, which has been used for gene prediction in the paper, has been a program for more than 10 years.It may be different if a high-precision gene prediction program using DeepLearning comes out soon.
ゲノムアセンブルしてそこから遺伝子予測では精度が悪いので、非モデル生物で特定の遺伝子のcDNA全長を取りたい場合は、RNA-seq→Trinityでde novoアセンブルしたコンティグを使ったほうが良いのではと思ってます。
Genome assembling is not accurate in predicting genes from there, so if you want to take the full length of cDNA of a particular gene in a non-model organism, I think you should use a contig with RNA-seq→Trinity de novo assembling.
ただ、Trinityもキメラコンティグを出したりするので、出来たらcDNAをPacやナノポアなどで全長シーケンスして、アセンブルしないのが一番だと思いますが、まだそういったIsoSeqなどのデータを実際に使ったことはないです。
However, Trinity also issues chimeric contigues, so if possible, it would be best not to assemble cDNA by sequencing it in full length with Pac or Nanopore, but I have never actually used such data as IsoSeq.
それをまさに聞こうと思ってました笑、リファレンスがしっかりしてないとマッピングが微妙だからRNA-seq De novoアセンブルの精度次第になっちゃいますよね。非モデル生物で全長RNAをロングリードで読めるプロトコルが確立できてくるとかなり楽になりそうですね。コーディング領域だけでもアセンブル精度が高いと嬉しい人はたくさんいるでしょうし
I was just going to listen to that, but if the reference is not firm, the mapping is subtle, so it depends on the accuracy of the RNA-seq De novo assembly.I think it will be much easier if we can establish a protocol that allows non-model organisms to read full-length RNA with a long lead.I'm sure there are a lot of people who would be happy if the coding area alone had high assembly accuracy.
Whether feces floats or sinks is a scientific question
糞便が浮くか沈むかは科学的な問題である
https://research-er.jp/articles/view/116733
プレスリリースしか読んでおりませんが、クマは冬眠中に筋肉が衰えず、タンパク質合成・分解制御系(オートファジー・ユビキチンプロテアソームなど)の両者とも、冬眠に伴い顕著に抑制されるそうです。
https://research-er.jp/articles/view/116733
I've only read the press release, but it seems that bears do not lose muscle during hibernation, and both protein synthesis and degradation control systems (autophagy and ubiquitin proteasome, etc.) are significantly suppressed with hibernation.
drag & dropするようにゲノム編集
https://www.nature.com/articles/s41587-022-01527-4
Drag & Drop Genome Editing
https://www.nature.com/articles/s41587-022-01527-4
A 2-million-year-old ecosystem in Greenland uncovered by environmental DNA
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05453-y
環境DNAによって発見されたグリーンランドの200万年前の生態系
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05453-y
The last author Kenneth Poss was the first author of a paper reporting the heart regeneration in adult zebrafish 20 years ago on nature. This paper presents the applicaiton of the zebrafish-origin injury responsible enhancer elements to mammals and shows cardiac regeneration in mice. I didn’t know that they were coming this far
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590922004593#fig5
最後の著者であるケネス·ポスは、20年前に成体ゼブラフィッシュの心臓再生を自然について報告した論文の最初の著者でした。 この論文はゼブラフィッシュ由来の傷害の原因となるエンハンサー要素の哺乳動物への応用を示し、マウスにおける心臓再生を示している。 ここまで来るとは知りませんでした。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590922004593#fig5
これは面白い。zebrafishの骨格筋の新生筋線維形成でも特異的なプロモーターが働くので、哺乳類に応用するとアダルトなどでの筋線維形成を誘導できるかも?
That's interesting, because zebrafish's new muscle fiber formation in skeletal muscle also has a specific promoter, so maybe it can be applied to mammals to induce muscle fiber formation in adults and other places?
またしてもベニクラゲ。内容はずいぶんシンプルですが。
T. dohrniiのゲノムって、前に読まれてなかったっけ?
Once again, red jellyfish.The content is quite simple.
beauty of Shimomura
Didn't you read T. dohrnii's genome before?
どっちも380Mbpと400Mbpという結果です。
違いはちょっとサンプルの取り方で英語読み間違えてなければ、前に挙げて頂いた方は野生のポリプ1000個と未成熟クラゲ60匹を混ぜたもの、今回のは同一クローン1500個体を合わせたもので読んだ事とその後の遺伝子への注文の仕方だと思います。
Both results are 380 Mbp and 400 Mbp.
The difference is that if you don't misread the sample in English, the person who mentioned it before is a mixture of 1000 wild polyps and 60 immature jellyfish, and this one is a combination of 1500 identical clones, and how to order the gene afterwards.
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)01696-5
De novo birth of functional microproteins in the human lineage
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)01696-5
ヒト系統の機能性微小タンパク質のデノボ誕生
銀染ではなくて銅染?という方法があるらしいのですが、ご存じの方いますか?
https://twitter.com/meiosiva/status/1614199967098507264?t=EeDnYxIat2TnL1XwWuiwzA&s=19
Does anyone know that there is a method called copper dyeing instead of silver dyeing?
https://twitter.com/meiosiva/status/1614199967098507264?t=EeDnYxIat2TnL1XwWuiwzA&s=19
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01570-7
A team from Harvard Medical School suggests aging is caused by cumulative loss of epigenetic marks. The team induced aging on mice by genetical engineering and reversed part of the epigenetic changes with the injection of AAVs (adeno-associated viruses) carrying OSK genes. And they claimed aging can be driven forward and backward by manuipulating the epigenome. Study published on Cell last Thursday.
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01570-7
ハーバード大学医学部の研究チームは、老化はエピジェネティックマークの累積的な喪失によって引き起こされると示唆しています。 研究チームは、遺伝子工学を通じてマウスの老化を誘導し、OSK遺伝子を搭載したAAV(アデノアソシエートウイルス)を注入し、エピジェネティック変化の一部を反転させた。 そして彼らは、エピゲノムを製造することによって、老化を前進および後退させることができると主張しました。 研究は先週木曜日にセルに掲載されました。
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
Illumina releases their own synthetic long read
https://sapac.illumina.com/company/news-center/press-releases/press-release-details.html?newsid=4ed94908-fde0-4a34-974d-03a0f4252053
Illumina独自の合成ロングリードをリリース
https://sapac.illumina.com/company/news-center/press-releases/press-release-details.html?newsid=4ed94908-fde0-4a34-974d-03a0f4252053
“Illumina Complete Long Reads leverages "land-marks" on the original long, single-molecule fragment analyzed in combination with unmarked standard reads to generate highly accurate, complete long reads. This innovative long-read solution overcomes the pain points of other on-market solutions - high DNA input requirements, complex workflows with low throughput, highly variable results and the need for additional dedicated instruments.”
「IlluminaCompleteLongReadsは、マークされていない標準読み取りと組み合わせて分析された元の長い単一分子フラグメント上の「ランドマーク」を利用して、非常に正確で完全な長い読み取りを生成します。 この革新的な長期読み取りソリューションは、高いDNA入力要件、低いスループットを持つ複雑なワークフロー、非常に可変的な結果、および追加の専用機器の必要性など、市販の他のソリューションの課題を克服します。」
It seems like they randomly mutagenize the template molecules and then fragment them followed by sequencing so they can assemble the fragments. Probably they also sequence the intact molecules and map them back to the contig?
彼らはランダムにテンプレート分子を変異させ、その後に断片化し、その断片を組み立てることができるようにシーケンス処理を行うようです。 おそらく、彼らは無傷の分子を配列し、それらをコンティグにマッピングし直しますか?
It would work if it’s just for SNP calling
SNPコールだけであれば動作します。
Illuminaは過去に合成ロングリードとしてMoleculoを販売してすぐに止めたことがありますが、今回はどうなんでしょう。PacBioのHiFiにコスト、精度ともに負けそうな気がしますけど、スループットの情報がなさそうなのでよくわかりませんね。
Illumina has sold Moleculo as a synthetic long lead in the past and stopped immediately, but what about this time?I feel like I'm going to lose to HiFi of PacBio in both cost and accuracy, but I don't know because there seems to be no throughput information.
正直あまり魅力が分かりませんでした、めっちゃ安ければ考えてもいいかもしれないですね
To be honest, I didn't really understand the charm. If it's very cheap, it might be good to think about it.
https://link.springer.com/article/10.1007/s44211-023-00280-1
eDNA抽出の際にRNAlaterを使うよりもbufferATLを使った方が濃度を濃く取れるらしいです。
https://link.springer.com/article/10.1007/s44211-023-00280-1
It seems that the concentration can be increased by using bufferATL rather than using RNAlater when extracting eDNA.
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
商品化されたらしいですね
https://www.nature.com/articles/s41587-023-01685-z
I hear it's been commercialized.
https://www.nature.com/articles/s41587-023-01685-z
scRNA-seq興味あるのですがDropseqを自分でやるのは難しそうなので、簡単に手が届くようになるのはうれしいです。実際こっちが主流になっていくのでしょうか?高くてもDropseq外注したほうが良いという意見もありそうですが、木島さん的にはどうですか?
I'm interested in scRNA-seq, but it seems difficult to do Dropseq myself, so I'm glad that it's easy to reach.Is this actually going to become the mainstream?Some people think it's better to outsource Dropseq even if it's expensive, but what about Mr. Kishima?
今のところ10x一強かなと言う感じがするんだけど、新興勢力がボコボコ出てきてるのでなんとも言えない気がするかなー
So far, I feel like it's just over 10x, but I don't think I can say anything about it because emerging powers are popping up and down the drain.
10xはやっぱめっちゃ高い機械とキットが両方必要なのがネックで、その点特別な機械がいらないParseのSPLiT-seqとかは興味ある(結局キットは高いんだけど)
https://www.parsebiosciences.com/
The bottleneck of 10x is that it requires both a very expensive machine and a kit, and I am interested in Parse's SPLiT-seq, which does not require a special machine (although the kit is expensive after all).
https://www.parsebiosciences.com/
日本で展開してるかは知らないけどParseは北米では結構勢いあるイメージ
I don't know if it's developing in Japan, but Parse has a strong image in North America.
Parseはキット自体は結構高いんだけど、細胞を溜め込んで大量にマルチプレックスできるので解析したいサンプルがたくさんある場合はお得だと思う(核RNA-seqなのでフリーザーに固定した各サンプルを一ヶ月くらい?保ストックしてプールできる)
Parse's kit itself is quite expensive, but it can store cells and multiplex a lot, so if you have many samples you want to analyze, I think it's a good deal. (Since it's nuclear RNA-seq, each sample fixed to the freezer is about a month?)can be stored and pooled)
あとはDrop-seq, inDropあたりの設備を持ってるラボと共同研究という形でやらせてもらうのがいいのでは
Also, I think it would be better to do it in the form of collaboration with a lab that has facilities for Drop-seq, in Drop.
水産無脊椎でもDrop-seq持ってるラボあるよね、聞いてみたら?
https://elifesciences.org/articles/66954
Why don't you ask if there's a lab with Drop-seq even in marine invertebrates?
https://elifesciences.org/articles/66954
小祝さんと共同研究していて、実際に花粉をDropSeqで読んでもらいました。
I was doing a joint study with Mr. Kogai, and I actually had him read pollen on DropSeq.
個人的にはDrop-seqあんまり好きじゃないんですけどね、細胞のロスがかなり多いしPCRバイアスも他の技術と比べて強い気がします
Personally, I don't like Drop-seq very much, but I think there's a lot of cell loss and PCR bias is stronger than other technologies.
今日xeniumのwebinar見てましたが、500遺伝子しか分からなくてもやっぱり細胞内局在までわかる空間トランスクリプトームを行うのが良いのかなと思いました。500個の遺伝子の検出率を揃えないといけないと言うのはバルクのRNAseqで補正するのかなとか難易度は高そうですけど、お値段はvision程度だとか。
I was watching Xenium's webinar today, and I thought it would be better to perform a spatial transcriptome that can understand the localization of the cell even if only 500 genes are understood.If you have to match the detection rate of 500 genes, it seems difficult to correct it with the bulk RNAseq, but the price is about vision.
visium
ビジウム
ゼニウムってターゲット型になったんですね。どうやって標的RNA増やすんですか?
Genium has become a target type.How do you increase the target RNA?
ターゲットにハイブリすると環状になってローリングサークルアンプリフィケーションで増えるそうです。
If you hybridize to the target, it becomes a ring and increases with rolling circle amplification.
- Kijima Yusuke
- Parseはキット自体は結構高いんだけど、細胞を溜め込んで大量にマルチプレックスできるので解析したいサンプルがたくさんある場合はお得だと思う(核RNA-seqなのでフリーザーに固定した各サンプルを一ヶ月くらい?保ストックしてプールできる)
僕の場合たくさんあるわけではないですが、ウミウシ細胞内に褐虫藻細胞がいくつもいるので、核RNAseqのほうがいいのかもしれないですね...
In my case, I don't have many, but there are many brown algae cells in the sea urchin cells, so nuclear RNAseq might be better......
じゃあアレイからオーダーメイドなんですか?
Then, is it custom-made from the array?
- Kazutoshi Yoshitake
- 小祝さんと共同研究していて、実際に花粉をDropSeqで読んでもらいました。
結局シングルセルやりたいなら小祝先生なんですかね
After all, if you want to do a single cell, you're a congratulatory teacher.
- Kijima Yusuke
- じゃあアレイからオーダーメイドなんですか?
非モデルだとオーダーメイドするしかなさそうです。ただ、難易度は高そうです。
If it is a non-model, it seems that we have no choice but to make it custom-made.However, the difficulty level seems high.
- Kazutoshi Yoshitake
- 非モデルだとオーダーメイドするしかなさそうです。ただ、難易度は高そうです。
in situは解像度高くてキレイだなーと思っていましたが、モデル生物でしかできないのかと思っていました。非モデルでもオーダーメイドすれば可能性はあるんですね
I thought in situ was beautiful with high resolution, but I thought it could only be done with model organisms.So there's a possibility if it's custom-made even if it's not a model.
またいつもの?出る出る詐欺になりそうですが、xeniumは今年中に?5000遺伝子にバージョンアップするとか言ってました。本当なら今後はxenium一択でよさそうに思ってしまいましたが、これをオーダーメイドで一発でうまくいくのかというと厳しそうな気がしています。
The usual? It's going to be a scam, but will xenium come out sometime this year?They said they would upgrade the version to 5000 genes.If it's true, I thought xenium would be a good choice from now on, but I think it's hard to say if it's a custom-made one shot.
visiumの細かいやつが出るって話ありましたよね?それは出る出る詐欺で終わりそうなんでしょうか?
出たとしてもシーケンス代が~って話なんでしたっけ
Did you say that the detailed visium will come out?Is it likely to end with fraud?
Even if it comes out, the sequence fee is...
- 溝端秀彬
- visiumの細かいやつが出るって話ありましたよね?それは出る出る詐欺で終わりそうなんでしょうか?
出たとしてもシーケンス代が~って話なんでしたっけ
そっちは出なそうな感じになってきましたよね。
It's starting to feel like it won't come out there.
そうなんですね
そっちはStereo-seqの商品化を待つしかなさそうですね
I see.
There seems to be no choice but to wait for the commercialization of Stereo-seq.
3mm直径でいいならおそらくCurioのSlide-seqがいいかと
https://curiobioscience.com/
If 3mm diameter is okay, Curio's Slide-seq is probably good.
https://curiobioscience.com/
で商品化されてる
be commercialized in
木島さんがinterstellerのテストデータかなんかで使ってたやつですよね、10倍もあるんですね
3nmなら十分だと思ってますが、日本で提供されてるのかよく分かりません
Mr. Kishima used to use the data for the interstellar test, which is 10 times more.
I think 3nm is enough, but I'm not sure if it's provided in Japan.
興味あったら買う買わない置いておいてQuote取ってみるのがいいと思う
If you're interested, I think it's better to buy, not buy, leave it behind and try Quote.
たけえ
fire
たっか、150万ですねぇ
I mean, 1.5 million.
でも8タイルだからvisiumと変わらないんですかね
But since it's 8 tiles, it's no different from visium.
まあそうだね、サイズが3mm x 3mmなのでVisiumより小さいけど
Well, the size is 3mm x 3mm, so it's smaller than Visium.
上手くやれば3mm四方でも見たいところは見れそうですが、8サンプル同時にライブラリ調製しなきゃいけないんですよね?
もうちょい細かい枚数で売ってほしいですね笑
If I do well, I can see what I want to see even if it's 3mm square, but I have to prepare the library at the same time, right?
I would like you to sell them in smaller quantities.
いや、多分一枚使って残り七枚は保存できると思うよ
No, I think I can use one and save the remaining seven.
あ、そうなんですか!じっくりHP読んでみます。spatialやる計画で助成金応募してるので当たるといいなぁ
Oh, really?I'll read the website carefully. I'm applying for a subsidy with a plan to do a special, so I hope I get it right.
でも、昨日のxeniumに比べると解像度が荒いなぁという印象です。
However, compared to yesterday's xenium, I have the impression that the resolution is rough.
↓Xeniumの例(昨日の鈴木穣先生の結果のほうがきれいでした)
↓Examples of Xenium (Yesterday's result of Ms. Furu Suzuki was prettier)
めちゃくちゃタイムリーですね
僕の場合これでも良さそうですが、in situに比べると確かに油絵みたいにぼやけてますね
It's really timely.
In my case, this is fine, but compared to in situ, it's definitely blurry like an oil painting.
なるほど、Xeniumってもはやシークエンサー使わないんですね。勘違いしてました。
パドロックプローブでRCAしてsmFISHか
I see, Xenium is no longer used as a sequencer.I misunderstood.
RCA to smFISH with padlock probe?
Padlock probe + RCAで増やしたあとSOLiDで読み出すFISSEQっていう技術が2014年に出てたので特許とか大丈夫なのかなと思ったんですが、開発者のGeorge Churchがサイトにいるし10xに買収されたんですかね
https://www.10xgenomics.com/in-situ-technology
In 2014, a technology called FISSEQ, which is read by SOLiD after increasing it by Padlock probe+RCA, came out, so I thought it would be okay to use a patent, but the developer George Church is on the site and was acquired by 10x.
https://www.10xgenomics.com/in-situ-technology
種特異プローブ組まずにこの解像度でtranscriptomeスケールで読みたいならやっぱExSeqのワークフローですかね、、でもXeniumの商品化まで来てるならFISHの部分をSOLiDなりIn situ seqに置き換えるだけなので割とすぐかもしれません
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aax2656
If you want to read on the transcriptome scale at this resolution without a species-specific probe, it might be an ExSeq workflow, but if you've come to commercialize Xenium, you just have to replace the FISH with SOLiD or Insightq, so it might be relatively quick.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aax2656
数個ではなくて、500個だそうです。どうやってそんなに色を区別するのだろう…
It's not a few, it's 500 pieces.How do you distinguish colors so much?
基本MERFISHの応用だと思います
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa6090
I think it's a basic application of MERFISH.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa6090
- Kijima Yusuke
- 基本MERFISHの応用だと思います
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa6090
開きたいけど、ウェブページが開けないです…
I want to open it, but I can't open the web page...
Visiumのオーサーが作ったHDSTも似たような感じでmultiplex smFISHですね
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765407/
The HDST created by Visium's author is similar to multiplex smFISH.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765407/
Pubmedでどうでしょう
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662681/
How about Pubmed?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662681/
ありがとうございます。開けました。
Thank you.I opened it.
そうです
That's right
SNVでも検出可能だとか。
It can be detected on SNV.
データに興味がある方はぜひ見てみてください。
If you are interested in the data, please check it out.
- 浅川修一
- そこでエラーの処理が大事みたいに書いてあるけど、そこはどうするの?
MERFISHの話ですかね。シンプルに各RNAに対応する組み合わせ蛍光シグナルのコードが十分違うようプローブをデザインするということだと思います
Are you talking about MERFISH?I think it simply means designing probes so that the code of the combination fluorescent signal corresponding to each RNA is sufficiently different.
そうですね。smFISH (single molecule fluorescent in situ hybridization)というやつです
そうですね。smFISH(単一分子蛍光insituハイブリダイゼーション)というやつです
RCAで形成された、DNAの球だね。AFsanaがPhi29でリピート合成した時全然、電気泳動でアガロースに入っていかなかった。それでなにかのNGSの原理図を見た時RCAでスライド上にDNAの塊ができている図が示されていて、ああ
It's a DNA sphere formed by RCA.When AFsana repeatedly synthesized it with Phi29, it did not enter agarose by electrophoresis at all.So if you look at some kind of NGS principle diagram, RCA shows a block of DNA on the slide, and it's like, oh.
あーそれはまた別の話ですね。MERFISHはRCAかませずに普通にRNAから直接FISHします。話題になっていた10xのXeniumは一度RCAでプローブの配列を増幅して蛍光強度を強めてるんだと思います
Oh, that's another story.MERFISH normally FISHs directly from RNA without RCA.I think the 10x Xenium, which was the talk of the town, is amplifying the sequence of probes with the RCA and increasing the fluorescence intensity.
ちなみにその原理図はBGIのDNBSEQだと思います(塊は界隈ではDNA nanoballって呼ばれてます)。あれはPhi29じゃないと思うんですけどね。
By the way, I think the principle diagram is DNBSEQ of BGI (the lump is called DNA nanoball in the neighborhood).I don't think that's Phi29.
ウェスターンなどでハイブリさせるとき、1回ブリーチすると2回目はかなりシグナル強度が下がるから、こんなに何回もハイブリさせられるのだなぁとびっくり。
I was surprised to hear that the signal strength decreases a lot when I bleach it once in a western style, so I was surprised to hear that it gets hybridized so many times.
Strand displacementは酵素の問題じゃなくてハイブリする場所が複数ある時の話でしたね
Strand displacement wasn't about enzymes, it was about multiple places to hybridize.
- Kazutoshi Yoshitake
- ウェスターンなどでハイブリさせるとき、1回ブリーチすると2回目はかなりシグナル強度が下がるから、こんなに何回もハイブリさせられるのだなぁとびっくり。
ここでいうブリーチとは同じ強い光を当てて蛍光プローブをダメにしているだけで、プローブ自体はくっついたままになっているみたい?
十分長い領域が識別部位として使われていそうなので、くっついたままで良いのですね。
Is it like the bleach here that only blasts the fluorescent probe by shining the same strong light, but the probe itself remains stuck together?
It seems that the area is long enough to be used as the identification area, so it's okay to keep it stuck together.
なるほど。そうすると、近いうちに5000遺伝子対応というのも可能な気がしてきました。
I see. Then I feel that it is possible to have 5000 genes in the near future.
10000遺伝子まではDemonstrationされてます
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1049-y
Up to 10000 genes are demonstrated.
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1049-y
ここではプローブを洗い流してるように見えるけどどうなんでしょうね。
It looks like the probe is being washed away here, but I don't know what it is like.
ぱっと見た感じの図はとても似ていますね。
The drawing looks very similar.
- Kijima Yusuke
- ここではプローブを洗い流してるように見えるけどどうなんでしょうね。
確かにこっちはストリッピングバッファーで洗浄して洗い流していますね。そのためかMERFISHと比べると画像がぼやけて見えるような気がしました。
It is true that this is washed with a stripping buffer.Maybe that's why I felt the image looks blurry compared to MERFISH.
- 浅川修一
- これと原理的にとても近い感じのことを25年前にやってたんです。引用されてないんですかね。
まんまっすね。すごい
That's right. Awesome.
先日の新領域の鈴木穣先生のウェビナーで、10x genomics社のXeniumについての発表の録画が公開されました。
http://email.10xgenomics.com/NDQ2LVBCTy03MDQAAAGKfCyaoyhZmd-tmOdWW3YpQ-_OxGVHJBAxxbG2eBFYqHeiBcjUnZlzRIdf3t5AvPmcd4IxfJA=
40分くらいからxeniumの結果が出てきます。
A recording of 10x genomics' announcement about Xenium was recently released on the webinar of Ms. Atsushi Suzuki in a new area.
http://email.10xgenomics.com/NDQ2LVBCTy03MDQAAAGKfCyaoyhZmd-tmOdWW3YpQ-_OxGVHJBAxxbG2eBFYqHeiBcjUnZlzRIdf3t5AvPmcd4IxfJA=
The result of xenium will come out in about 40 minutes.
先日の10x Genomics大崎さんによるXenium、Visium HDなどについてのウェビナー録画が公開されました。
http://email.10xgenomics.com/NDQ2LVBCTy03MDQAAAGKgcDTpo4-a308VSPV7pW52VlfGVVbct3j2JRh5Bj9Jih6D5mQl62rZ3nmCgNAY1BPNyXFELc=
Recently, 10x Genomics Osaki released a webinar recording of Xenium, Visium HD, etc.
http://email.10xgenomics.com/NDQ2LVBCTy03MDQAAAGKgcDTpo4-a308VSPV7pW52VlfGVVbct3j2JRh5Bj9Jih6D5mQl62rZ3nmCgNAY1BPNyXFELc=
ヒトは生まれた時に生涯の卵の数が決まってますが、長命種は生まれた後も、長期間卵を作ることができる。これが長期間生殖を続けることにつながっているのかも。
https://www.nature.com/articles/s41467-023-36284-8
Humans have a fixed number of eggs for life at birth, but long-lived species can produce eggs for a long time even after birth.This may lead to long-term reproduction.
https://www.nature.com/articles/s41467-023-36284-8
「バイオDBとウェブツール」(2022)というという本をKindleで購入しました。Kindleのスクリーンショットを撮って講義資料として配布すること自体は問題ないようなので、PDFに変換したものを共有フォルダに入れました。
「\\share.s\shared\Book\バイオDBとウェブツール.pdf」
日本の遺伝研の統合DBチームが執筆したようで、彼らのDBが多めに紹介されている内容ではありますが、皆さん一通り見ておくと良いかなと思います。
個人的には、黒川先生、森先生たちのMicrobeDBがMicrobe Datahubというものに変わろうとしているのだなぁ(でもまだ未公開)という情報が面白かったです。
I bought a book called BioDB and Web Tools (2022) from Kindle.There seems to be no problem with taking screenshots of Kindle and distributing them as lecture materials, so I put the PDF version in the shared folder.
US>\\share.s\shared\Book\BioDB and Web Tools.pdf
It seems to have been written by the integrated DB team of the Japanese Genetic Research Institute, and their DBs are introduced a lot, but I think it would be good for everyone to take a look.
Personally, it was interesting to hear that Mr. Kurokawa and Mr. Mori's MicrobeDB is changing to something called Microbe Datahub (but it hasn't been released yet).
先週の水産学会で興味深かった内容を忘れないうちにメモ代わりに書いてみました。
・海洋大 松下芳之
CRISPR/Cas9でのノックインの時に、ドナーDNAとしてdsDNAではなく、ノンターゲット鎖(逆鎖のほう?)のssDNAを使うことで、ゼブラフィッシュでノックイン効率を20%->90%程度に上昇させることが可能。両端に組み換え箇所の配列に相同な1000塩基を付与しておく。
・北大 西村俊哉
CRISPR-Cas13dを用いたノックダウンではメダカでモルフォリノオリゴ以上のノックダウン効率を達成。発表者は過去にモルフォリノオリゴも使用していたけど、Cas13dのほうが毒性も低くノックダウン効率も高いので今後はCas13dを使いたいとのこと。ただ、ガイドRNAが一つだけだとうまく行かないこともあるので、2,3個のガイドRNAを混ぜて使うほうが良いのではとのこと。
・(発表者忘れました)
セントロメア領域はヘテロ接合度が低いらしい… (セントロメア領域を推定する確かな手法は聞いたことが無いので、確かめてみたいと思いました)
・近縁種ゲノムでscaffoldingをするソフト…RagTag
Structureのような集団構造解析?…Popcluster
・工樂先生
HiC scaffoldingソフト…YaHS (SALSAよりも長く伸ばしてくれるみたいです。現在試しに実行中)
Before I forget what was interesting at the Fisheries Society last week, I wrote it down instead of taking notes.
·Yoshiyuki Matsushita, Marine Corporation
By using ssDNA of non-target chain (reverse chain?) instead of dsDNA as donor DNA when knocking in CRISPR/Cas9, the knock-in efficiency can be increased to about 20%->90% with zebrafish.1000 bases identical to the arrangement of recombinant parts are imparted to both ends.
·Toshiya Nishimura, North University
Knockdown using CRISPR-Cas13d achieves knockdown efficiency of more than morpholine oligo with killifish.The presenter also used morpholine oligos in the past, but Cas13d is less toxic and more knock-down efficient, so he wants to use Cas13d in the future, but it may not work with just one guide RNA, so it would be better to mix two or three guide RNAs.
·(I forgot the presenter)
The Centromere region seems to have low heterozygosity... (I've never heard of a reliable method of estimating the Centromere region, so I wanted to check it out.)
·Software for scaffolding in closely related genomes…RagTag
Structure-like collective structural analysis?...Popcluster
·Teacher of Kogaku
HiC scaffolding software…YaHSSAIt seems to extend longer than SALSA.currently running as a trial)
最近話題のChatGPTの最新版GPT-4は月2000円課金しないと使えないので、研究費で支払って使ってみました。
結果は…、たぶん使えるときもあると思うけど、GPT-3.5の時と同じく平気で嘘をつくのは調べものに使うにはつらいなと思いました。ニシオンデンザメの和名が「グリーンランド・サケガワイウオ」となっていたり、脊椎動物と言っているのに貝を出してきたり。
4月中は使えるので、気になる方は
https://chat.openai.com/chat/
を開いて
ID: suikoucalender@gmail.com
password: suikou0358417522
でログインして使ってみてください。
The latest version of ChatGPT, which has recently become a hot topic of conversation, cannot be used without charging 2000 yen per month, so I paid for the research and used it.
The result is... I think there are times when I can use it, but I thought it would be hard to use it as a research tool to lie without hesitation as in GPT-3.5.The Japanese name of the python shark is "Greenland salmon gawaio," or even though it is called a vertebrate, it produces shellfish.
You can use it during April, so if you're interested
https://chat.openai.com/chat/
with open
ID: suikoucalender@gmail.com
password: suikou0358417522
Please log in at and try using it.
グリーンランド・サケガワイウオ(笑)!私もGPT-3.5でいろいろ遊んでみましたが、出所不明のいい加減な情報を正しい情報に混ぜてそれらしく説明してくるので、正確な情報を取得する目的には使いにくいですね。
Greenland salmon roe fish! I've played with GPT-3.5, but it's hard to use it to get accurate information because it explains it by mixing irresponsible information with the correct information.
完全に見落としていたので今更ですが、
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpops/advpub/0/advpub_2023O001/_pdf/-char/ja
今回はハンドウイルカじゃなくてスジイルカなんですね。
I completely overlooked it, so it's too late,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpops/advpub/0/advpub_2023O001/_pdf/-char/ja
This time, it's not a hand dolphin, but a suji dolphin.
へぇ、また胸ビレがあるイルカが出てくるのですね。珍しいと言っても、この頻度で種を超えて出てくるということは、原因を考察する手がかりになりそうですね。
Oh, another dolphin with a chest fin appears.Even though it's rare, the fact that it comes out over species at this frequency seems to be a clue to the cause.
元々この程度の腹びれがあるものは報告に上がってないだけで実はいるみたいですね。ハラビレイルカのはるかがあれほど有名になったのは骨まで左右で完全な腹びれが形成されていたことだと思います。でも研究をするには毎回このくらいのものも報告してきてほしいですねー。今回もサンプル色々とってあるみたいですし、使う場合は日鯨研あたりに聞いたらもらえるんじゃないですかね。
Those with abdominal fins like this seem to bear fruit just because they haven't been reported.I think Haruka Harabile dolphin became so famous because it had complete abdominal fins on the left and right sides of the bones.But I would like you to report this much every time to do research.There seems to be a lot of samples taken this time too, so if you want to use them, I think you can ask around Nikkaiken.
- Ashley Rinka Smith
- 完全に見落としていたので今更ですが、
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpops/advpub/0/advpub_2023O001/_pdf/-char/ja
今回はハンドウイルカじゃなくてスジイルカなんですね。
情報ありがとうございます!
お三方とも腹びれイルカプロジェクトのメンバーだったと思うんですけど何か報告受けたりしてます?🤔
サンプル分けていただけるなら欲しいですねー
Thank you for the information!
Asakawa Shuichi Corporation
I think all three of you were members of the Dolphin Project. Have you received any reports?🤔
If you can share the samples, I would like it
三重大の鯨類研究センターですね。
It is a triple whale research center.
アシナガキアリ(日本にもいるらしい)には女王アリ、働きアリ、雄アリがいますが、それを決定する仕組みが面白いそうです。
このアリにはR型/W型の2系統のゲノムがあり、
女王アリ:R/Rの2倍体
働きアリ:R/Wの2倍体
雄アリ:R型1倍体細胞とW型1倍体細胞のキメラ
になっているとのこと。
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf0419
There are queen ants, worker ants, and male ants among the Asinagaki ants (which seem to be in Japan), and they say it is interesting to see how they are determined.
These ants have two genomes, R-type and W-type,
queen ant: diploid of R/R
Working ants: diploid of R/W
Male ants: Chimera of R-type and W-type diploid cells
It is said that.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf0419
RNA polymerase IIによる転写速度は加齢と共に早くなり、これが不正確な転写→老化につながるらしい。種によって寿命は違うけど、転写速度(あるいは転写速度の加齢に伴う変化率?)も寿命の長短によって違うんだろうか?遺伝子サイズと寿命は相関するというデータもあり、興味深い。
It seems that RNA polymerase II increases transcription speed with age, which leads to inaccurate transcription → aging.Life expectancy varies from species to species, but does the rate of transcription (or the rate of change in transcription rate with age?) also vary depending on the length of life?Some data show that gene size and life expectancy are correlated, which is interesting.
This week’s Science is crazy
https://www.science.org/toc/science/current
今週の科学はクレイジーです
https://www.science.org/toc/science/current
ゲノム目白押しですごいですね!
これも寿命グループには重要なんでしょうか?
https://www.science.org/doi/10.1126/science.add7631
It's amazing that the genome is pressed!
Is this also important for life groups?
https://www.science.org/doi/10.1126/science.add7631
Yeastだけど面白いな
Yeah, but it's fun
すいませんなんか誤爆しました
I'm sorry, but I accidentally bombed
僕宛ですね、ありがとうございます!
It's for me, thank you!
https://www.macrogen-japan.co.jp/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=295
当研究室で良く発注しているHiSeqXは7月までだそうです。その後は用途によるけどDNBSEQなのかなぁ。
https://www.macrogen-japan.co.jp/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=295
I heard that HiSeqX, which we often order in our laboratory, is until July.After that, it depends on the use, but I wonder if it's DNBSEQ.
マクロジェンから連絡がありまして、ニシオンデンザメのサンプルについては
===============
PacBioのRevio件は予想より少し長くなりますが、
進めています。(一部データは取得済み)
少しお待ちしていただければ幸いです。
===============
とのことなので、期待できそうです!
HiSeqX代替のNovaseqX plusについては、
1レーン(150PE)のデータ量(目安):375Gb (HiSeqの4倍弱)
価格:295,000円(税別)(HiSeqの2倍)
とのことなので、HiSeqXよりも1bpあたりの単価は半分になるけど、これまでの倍の30万円かかるというところで少し出しづらくなった感じです。
シングルセルなど大量に読む必要がある場合には良いですが、通常はDNBSEQなどになるのかなぁという感じです。
Macrogen contacted me about the sample of the python shark
===============
The Revio case of PacBio will be a little longer than expected,
We are proceeding (some data have been retrieved)
I would appreciate it if you could wait a little longer.
===============
That's why I think I can look forward to it!
For HiSeqX alternative NovaseqX plus, please refer to the,
Approximate data volume per lane (150PE): 375Gb (just under 4x HiSeq)
Price:null,295,000 (tax excluded) (double HiSeq)
So, the unit price per bp is half as high as HiSeqX, but it costs 300,000 yen, twice as much as before, so it's a little hard to pay.
It's good if you need to read a lot such as a single cell, but it's usually DNBSEQ.
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/c2c7eba5ab298e06714bd966487caf726b400a8a&preview=auto
黒河内さん、かずさDNAの白澤さんとご一緒させていただいたマツタケのゲノム解析のことがヤフーニュースに載ってました。要約するとHiFiすごいっていう研究でした。。。
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/c2c7eba5ab298e06714bd966487caf726b400a8a&preview=auto
Yahoo News reported on the genome analysis of matsutake mushrooms with Mr. Kurokawauchi and Mr. Shirazawa of Kazusa DNA.In summary, it was a study that said HiFi is amazing...
DNBSEQについて、ゲノムリードに見積もりを取ってみました。
DNBSEQ用のネイティブなライブラリーというのは環状化したssDNAということのようです。
IlluminaはアダプターつけてPCRすれば終わりだったのですが、DNBSEQはそんなに単純に出来るわけではなさそうです。
以前BGIに見積もりを取ったときは、直鎖状のdsDNAをコンバートしてくれる代金込みで13万円だったので、BGIに頼むことになるのかなぁと思っているところです。再度BGIに見積もりを取ってみようと思います。
=============================
お世話になります。ゲノムリード 谷口誠です。
お問い合わせありがとうございました。遅くなり申しわけございません。
NovaSeq6000の場合、SPフローセル(2レーン)を使えば
1レーンあたり 120Gbp程度取得できます。
ただし、データ量はあくまで参考値であり、保証値ではありません。
ライブラリーの濃度、サイズ、PhiXの添加量により左右されます。
現状でのシーケンスコスト(原価)が、1レーン30万円+税かかってしまいます。
もう少し安くできないかイルミナとも相談して検討しているところです。
DNBSEQの場合
DNBSEQ用のライブラリーを調整して、環状化したssDNAの状態にしておいていただ
けるのであれば
1レーン 約120Gbpで 13万円+税です。
ただ、イルミナのようにPhiXが市販されていないため、アンプリコンシーケンスの
ように
塩基多様性が低い場合は、何か他のライブラリーを混ぜて塩基多様性を確保する必
要があると思います。
イルミナのライブラリーをMGI用にコンバージョンしてDNBSEQでランをすることも
可能です。
コンバージョンを行う場合、フローセル全体(2レーンあるいは4レーン)を
全てコンバージョンしたものを流す必要があります。プライマーを選択できないた
め。
現状ではあまりコンバージョンの依頼が無い(NexteraかTruseqか、シングルか
Dualかが全て一致する必要がある)
ので、コンバージョンをご希望の場合は、1フローセルを買い取ってもらう場合の
み対応しています。
将来的に同じような案件が集まるようになれば、レーン単位でのシーケンスもお受
けできるようになると思います。
FCSフローセル 2レーンで165Gbp 35万円+税
FCLフローセル 4レーンで480Gbp 50万円+税
ライブラリーコンバージョン費用 4ライブラリーまで 5万円+税
代理店が入らないのであればもう少し安くはなります。
よろしくお願いいたします。
谷口 誠
------------------------------------------------------------
ゲノムリード株式会社 ←新しく法人となりました
(谷口歯科医院 口腔常在微生物叢解析センター)
760-0054 香川県高松市常磐町1-9-14
TEL:087-831-8020 FAX:087-831-8021
------------------------------------------------------------
Regarding DNBSEQ, I have taken a quote from Genome Lead.
The native library for DNBSEQ seems to mean cyclic ssDNA.
The Illumina would have ended with PCR with an adapter, but DNBSEQ doesn't seem to be that simple.
When I got an estimate from BGI before, it was 130,000 yen including the price for converting straight-chain dsDNA, so I'm wondering if I have to ask BGI.I would like to get an estimate from BGI again.
=============================
Thank you for your help.This is Makoto Taniguchi, Genome Lead.
Thank you for your inquiry.I apologize for the delay.
For NovaSeq6000, using SP flow cell (2 lanes)
You can get about 120Gbp per lane.
However, the amount of data is only a reference value, not a guaranteed value.
It depends on the library's concentration, size and amount of PhiX added.
The current sequence cost (cost) is 300,000 yen per lane plus tax.
I'm also discussing with Illumina to see if I can make it a little cheaper.
For DNBSEQ
The library for DNBSEQ was adjusted and kept in a cyclic ssDNA state
if you's the case
It costs 130,000 yen plus tax for about 120Gbp per lane.
However, since PhiX is not commercially available like Illumina, the amplifier control sequence is used
like
If base diversity is low, you must mix some other libraries to ensure base diversity
I think it's important.
You can convert the Illumina library for MGI and run with DNBSEQ
Yes, it's possible.
When converting, use the entire flow cell (2 lanes or 4 lanes)
You need to play the converted version of everything.Failed to select primer
eye。
Currently, there are not many conversion requests (Nextera, Truseq, or single)
Dual must match everything)
Therefore, if you would like to convert, I would like to ask you to purchase one flow cell
Only available.
If similar issues come together in the future, we will also receive a lane-by-lane sequence
I think I will be able to kick it.
165Gbp 円350,000 + tax for FCS flow cell 2 lanes
480Gbp +500,000 + tax for 4 lanes of FCL flow cell
Library conversion cost +50,000 for 4 libraries plus tax
If there is no agency, it will be a little cheaper.
Thank you.
sincerity of Taniguchi
------------------------------------------------------------
Genome Lead Co., Ltd. ← New corporation
(Taniguchi Dental Clinic, Center for Analysis of Plexus of Oral and Ordinary Microorganisms)
760-0054 Joban-cho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture 1-9-14
TEL:087-831-8020 FAX:087-831-8021
------------------------------------------------------------
BGIに再度見積もりを取りました。お値段は変わらず税抜きで12万円ほどでした。HiSeqXと同じライブラリーで注文できそうなので、今後はBGIにDNBSEQ-G400を依頼することになりそうです。
====================
アンプリコンシーケンス
機種:DNBSEQ-G400
合計費用:110,000円+9,000円+4,000=123,000円 (税別)
・ライブラリ作成+シーケンシング(PE150、1 lane、約340M pair reads/lane)
・初回サンプル送料値引き価格9,000円込
・AWSダウンロード納品4,000円込
・無料サンプルQC
・納期:約4週間
====================
また、DNBSEQでのPE250とPE300のシーケンスのみサービスを提供し始めました。
価格はPE150より高くなりますが、まず価格を送りしてご参考していただければと思います。
====================
アンプリコンシーケンス
機種:DNBSEQ-G400
合計費用:350,000円+9,000円+4,000=363,000円 (税別)
・ライブラリ作成+シーケンシング(PE250/300、1lane分、約60-100M pair reads/lane)
・初回サンプル送料値引き価格9,000円込
・AWSダウンロード納品4,000円込
・無料サンプルQC
・納期:約5週間
====================
作成済みのライブラリの実施について、ライブラリの事前評価は必要であるため、添付エクセル(Self Prepared Library Evaluation Form)のsheet 1よりライブラリ情報とインデックス情報はまとめてご記入してから、ご返送していただけますと幸いです。
I have re-quote to BGI.The price was about 120,000 yen without tax.I think I can order from the same library as HiSeqX, so I will probably ask BGI for DNBSEQ-G400 from now on.
====================
amplifier control sequence
Model: DNBSEQ-G400
Total cost: 110,000 yen + 9,000 yen + 4,000 = 123,000 yen (tax excluded)
·Library creation + sequencing (PE150, 1 lane, approximately 340M pair reads/lane)
·First sample shipping discount price includes 9,000 yen
·AWS download delivery includes 4,000 yen
·Free sample QC
·Delivery date: Approximately 4 weeks
====================
Also, we started to service only PE250 and PE300 sequences in DNBSEQ.
The price will be higher than PE150, but I would appreciate it if you could send me the price first and refer to it.
====================
amplifier control sequence
Model: DNBSEQ-G400
Total cost: 350,000 yen + 9,000 yen + 4,000 = 363,000 yen (tax excluded)
·Library creation + sequencing (PE250/300, 1 lane min, approximately 60-100M pair reads/lane)
·First sample shipping discount price includes 9,000 yen
·AWS download delivery includes 4,000 yen
·Free sample QC
·Delivery date: Approximately 5 weeks
====================
As a preliminary evaluation of the library is required for the implementation of the created library, I would appreciate it if you could fill out the library information and index information in sheet 1 of the attached Self Prepared Library Evaluation Form before returning it.
NovogeneにPacBio Revioの見積もりを取ってみると、最小90Gbase~で90万円程度になるようでした。
マルチプレックス可能かどうかは種によるそうです。
3種くらい混ぜられて、1種あたり1Gbaseくらいのゲノムであれば、Revioで読んでしまえば良さそうな気はします。
When I got an estimate for PacBio Revio from Novogene, it seems to be around 900,000 yen for a minimum of 90 Gbase.
It depends on the species whether multiplexing is possible or not.
If it's a genome of about 1 Gbase per genome, I think it's good to read it in Revio.
Inadvertent human genomic bycatch and intentional capture raise beneficial applications and ethical concerns with environmental DNA
https://www.nature.com/articles/s41559-023-02056-2
意図的な捕獲と捕獲による不注意なヒトゲノムは、環境DNAの有益な応用と倫理的懸念を引き起こす
https://www.nature.com/articles/s41559-023-02056-2
現在国際eDNA学会2023に参加しています。
口頭発表する外国の方たちはMiFishを使ったeDNA研究はルーチンになってきて、あとは組織的にどうやってモニタリングを継続するのか、体制づくりに興味があるという印象でした。
個人的には、MiFishはよく増えるのですが私のターゲットのD-loopは増えないことが多いので、高感度化を突き詰めている研究を期待していたのですが、すでにMiFishに固まりつつある現場では高感度化の方向性で改良した人は今回はいないようでした。
まだあと1日ありますが、気になった発表を備忘録として書いておきます。
・James Reimer (琉球大)
沖縄の複数地点のMiFish・サンゴ礁をCOIで調査。それに加えて小笠原のMiFish・サンゴ礁COI調査も行っていて、小笠原も沖縄と似た亜熱帯系の魚・サンゴ礁がいるという発表。まだどこに何がいるかを網羅するだけでも仕事になるのだなと思いました。
・Itsuki Hirayama (eDNA学会マニュアルで有名な源 利文 先生のラボ)(神戸大)
卵巣だけは特異的にメチル化度が低く、環境DNA中のDNAメチル化パターンをバイサルファイト法で調べると、いつ産卵しているかわかるらしい。組織特異的なメチル化パターンを突き詰めていけば、どの組織からeDNAが出ているかわかりそうだと思ったけど、そういう方向では研究を進めていないみたいでした。
・ゴーフォトンという会社のマイクロデバイスで濾過〜DNA抽出までを自動化
3分程度で終わるそうです。
https://youtu.be/vOZmZBgwR4w
に実演のデモがあります。日本の会社が開発中。市販化はまだらしいですが、将来的にはステリベクスフィルターと同じ程度の価格になるのではとのこと。抽出量が10ulと少なくできるので、インプットも少なくできるそうです。
全体的には、MiFishを使って網羅的に検出しましたという人と、特定の種をターゲットとして自分たちでプライマーを設計しましたという人が多く、昆虫用のプライマーなど、魚以外の網羅的なプライマー性能を評価しようとする人たちはいなかったのが残念でした。
eDNAから産卵期を調べようとしている人は何人かいて、総合すると下記のような手がかりが使えるようです。
・単純にeDNA量が増える(主に精子放出による)
・核/ミトコンドリア比が増える(精子にはほぼ核しかないため)
・eDNAのメチル化が下がる
I am currently participating in the International eDNA Association 2023.
Foreigners who make oral presentations had the impression that eDNA research using MiFish has become a routine, and that they are interested in establishing a system of how to continue monitoring systematically.
Personally, MiFish often increases, but my target D-loop often doesn't, so I was hoping for a study that focused on increasing sensitivity, but no one seemed to have improved the direction of increasing sensitivity in the field that was already solidified into MiFish.
I still have one more day, but I'll write down the announcement I'm interested in as a memorandum.
·James Reimer (Ryukyu University)
A COI study of MiFish coral reefs at several locations in Okinawa.In addition to that, I was conducting a survey of MiFish coral reefs in Ogasawara, and announced that Ogasawara also has subtropical fish and coral reefs similar to Okinawa, so I thought it would be a job just to cover where they are.
·Itsuki Hirayama (Professor Genji's lab famous for eDNA Society manual) (Kobe University)
Only the ovaries are specifically low in methylation, and it seems that if you examine the DNA methylation pattern in the environmental DNA by bisulfite method, you can see when they are spawning.I thought it would be possible to find out from which tissue eDNA came out by looking at tissue-specific methylation patterns, but it seemed that research was not being carried out in that direction.
·Automated filtering through DNA extraction with a microdevice of a company called GoFoton
It will be over in about three minutes.
https://youtu.be/vOZmZBgwR4w
There is a demonstration demonstration in .A Japanese company is developing it.It seems that it has not been commercialized yet, but in the future, it will be about the same price as the Stelibex filter.The amount of extraction can be reduced to 10ul, so the input can be reduced.
Overall, it was disappointing that many people said they used MiFish to comprehensively detect and design their own primers for specific species, and no one wanted to evaluate the comprehensive primer performance other than fish, such as insect primers.
There are some people who are trying to find out the spawning season from eDNA, and in total, the following clues can be used.
·Simply increase the amount of eDNA (mainly due to sperm release)
·Increased nuclear/mitochondrial ratio (because sperm has almost only nuclei)
·Methylation of eDNA decreases
マツタケゲノムについて当研究室はあまり貢献できていないのでなんともなのですが、東大農学部の森林のラボの方が提供したマツタケを使ってゲノム解析が行われました。そのマツタケがどこに生えていたのか共同研究者である私達も知らされておりませんが、追加でサンプルが必要になってサンプリングして頂いたときには既に誰かに取られたあとだったというマツタケならではの話もありました。
Although our laboratory has not been able to contribute much to the Matsutake genome, we conducted genomic analysis using Matsutake mushrooms provided by a forest lab at the University of Tokyo's Faculty of Agriculture.We, as co-researchers, have not been informed of where the matsutake was growing, but there was also a story unique to matsutake that it had already been taken by someone when they needed additional samples.
eDNA学会3日目のメモです。
・Daisuke Isobe (龍谷大学)(環境DNAでは結構有名な山中先生のラボの方)
MiFish-Uプライマーはアユに対して3塩基のミスマッチがあり、MiFish-Uプライマーではほとんど検出できない。そこでアユに一致した配列に変更したプライマーを混ぜるとアユも検出できた。アユ以外の種に関しては少しだけ検出感度が下がっているように見えた。
・Masaki Takenaka(信州大学)
水生昆虫用に特化した「MtInsects-16S」というプライマーセットの開発。ミトコンドリアの16Sを使っていた。バクテリアや藻類などがほとんど増えず、既存の採集による調査と90%以上の一致率を示していた。すごいと思ったけど、既に有名な水生昆虫用のプライマーとして「fwhF2-EPTDr2n」が知られているけど、それとは比較していないとのこと。皆さん好き勝手に作っているなぁという印象ではありました。
学会全体を通じてMiFishプライマーを使ったeDNA研究と、既存の目視や採集による調査手法を比較した発表は色々ありましたが、だいたい70%くらいの一致率しかなく、それぞれ30%程度は検出できない種がありました。
ウナギもMiFishでは種を同定できないらしいし、前述のようにアユなどそもそも増えない種がいるというのはまだまだ魚類検出用プライマーとして改良の余地があると感じました。
昨日書き込んだ3分で終わる微量チップは試供品をいただけることになりそうです。
This is a memo from the third day of the eDNA Society.
·Daisuke Isobe (Ryukoku University) (Mr. Yamanaka's lab, which is quite famous for its environmental DNA)
The MiFish-U primer has a three-base mismatch with respect to the ayu and is hardly detectable with the MiFish-U primer.Ayu could also be detected by mixing the modified primer into a sequence that matched the ayu.yu.As for species other than ayu, the detection sensitivity seemed to decrease a little.
·Masaki Takenaka (Shinshu University)
Development of a primer set called "MtInsects-16S" specialized for aquatic insects.I used a mitochondrial 16S.There was little increase in bacteria and algae, showing a consistency rate of more than 90 percent compared to existing collection surveys.I thought it was amazing, but they already know fwhF2-EPTDr2n as a famous primer for aquatic insects, but they don't compare it with that.I had the impression that everyone was making whatever they wanted.
Throughout the conference, eDNA studies using MiFish primers were compared with existing visual and collection methods, but there were only about 70 percent consistency and about 30 percent each species could not be detected.
It seems that eels cannot be identified by MiFish, and I felt that there is still room for improvement as a fish detection primer because there are species such as ayu that do not increase in the first place.
It seems that you will be able to get a sample of the trace chip that I wrote yesterday in 3 minutes.
2300種の蝶の分子系統樹・分布記録の解析から、蝶は1億年前にアメリカ大陸で誕生した可能性が高い事が分かった。
https://www.nature.com/articles/s41559-023-02041-9
Analysis of 2,300 species of butterfly molecular tree and distribution records showed that butterflies are likely to have been born in the Americas 100 million years ago.
https://www.nature.com/articles/s41559-023-02041-9
To answer Kinoshita-sensei’s question, why the experiment focused on NR instead of NAD?
Quote from paper: To determine the efficacy of small molecules that may protect hepatocytes against ethanol-induced acute hepatic injury, we tested nicotinamide riboside (NR), a substrate for NAD+, that has previously been shown to inhibit ethanol induced liver injury in a rodent model. (ref: doi: 10.1038/s41586-018-0645-6)
The paper doi: 10.1016/j.biopha.2020.110836
木下先生の質問に答えるために、なぜ実験はNADではなくNRに焦点を当てたのでしょうか?
論文からの引用: エタノールによる急性肝損傷から肝細胞を保護することができる小さな分子の有効性を決定するために、我々は以前に齧歯類モデルでエタノールによる肝損傷を抑制することが示されているNAD+の基質であるニコチンアミドリボシド(NR)を試験した。 (参照: doi: 10.1038/s41586-018-0645-6)
doi:10.1016/j.biopha.2020.110836
了解しました。彼らはNR投与後のNADレベルは測定しているのでしょうか?
OK. Are they measuring the NAD level after NR administration?
Not on this experiment apparently. But the reference did, quote:
The NAD+, NADP+, NAM, NMN, ATP, ADP and AMP Levels in liver tissues and HepG2 cells were analyzed with a Hypercarb column (100x2.1mm,3μm, ThermoFisher Scientific, USA) with UPLC-QTOF System (Infinity/6538, Agilent Technologies),
どうやらこの実験ではないようです。 しかし、参考文献は次のように引用している:
肝臓組織およびHepG2細胞のNAD+、NADP+、NAM、NMN、ATP、ADP、AMPレベルは、UPC-QTOFシステム(Infinity/6538、アジレントテクノロジーズ、100x2.1mm、3μm、ThermoFisher Scientific、USA)で分析された、
ありがとうございます。2020年に初めてシングルセルやったのと同じグループっぽいですね。着実に進めてる感あって凄いです…
Thank you.I think it's the same group as the first single cell in 2020.It's amazing that I feel like I'm making steady progress...
promoterのCpG ilandの密度で、脊椎動物の寿命が予測できる。これは魚にも当てはまりそう。
https://www.nature.com/articles/s41598-019-54447-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1755-0998.13774
The density of promoter CpGiland can predict the life of vertebrates.This may apply to fish, too.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-54447-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1755-0998.13774
Figure 1はぱっと見綺麗な相関だなと思いましたが、各分類群ごとに補正項が異なっていて、魚では特に大きく違う(↓表)ので一般化は難しそうかなと思いました。
https://www.nature.com/articles/s41598-019-54447-w/tables/1
At first glance, I thought Figure 1 was a beautiful correlation, but I thought it would be difficult to generalize because each classification group has different correction terms and it is especially different for fish (↓Table).
https://www.nature.com/articles/s41598-019-54447-w/tables/1
ええ、彼らも魚はあまりフィットしないということで、改めて魚だけでデータ増やしてやってます。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1755-0998.13774
Yes, they also don't fit well, so they are increasing the data with only fish.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1755-0998.13774
Sci Total Environ
. 2021 Aug 1;780:146534. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.146534. Epub 2021 Mar 18.
Resolving the effects of environmental micro- and nanoplastics exposure in biota: A knowledge gap analysis
Sciトータル環境
. 2021年8月1日:780:146534.doi:10.1016/j.scitotenv.2021.146534。 Epub2021年3月18日。
バイオタにおける環境マイクロおよびナノプラスチック暴露の影響の解決:知識ギャップ分析
Review Environ Pollut
. 2021 Dec 1;290:118101. doi: 10.1016/j.envpol.2021.118101. Epub 2021 Sep 3.
Ecological implications beyond the ecotoxicity of plastic debris on marine phytoplankton assemblage structure and functioning
環境汚染の確認
. 2021年12月1日;290:118101.doi:10.1016/j.envpol.2021.118101。 Epub2021年9月3日。
海洋植物プランクトンの集合構造と機能に対するプラスチック廃棄物の生態毒性を超える生態学的影響
以前プロモーター部位のCpG ilandの密度で寿命予測ができるという論文を紹介しましたが、それと関連して、CpGとトランスポゾンが生物種によるゲノムのサイズの違いを生み出してきたという論文。ニシオンデンザメのゲノムが大きいこと+繰り返し配列が多いことも関連しそうに思います。
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1921719117
Previously, we introduced a paper that predicts life expectancy based on the density of CpGiland, a promoter site, and related to this paper, CpG and transposon have created differences in genome size by species.I think it is also related to the large genome of the python shark and the large number of repeated sequences.
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1921719117
CpGの密度と寿命という話だけでは、いったい何の因果関係があるのだろうと思っておりましたが、CpG→転移因子の数→ゲノムサイズとなってくると、なるほど寿命と関係がありそうなゲノムサイズの話に結び付くのかと思いました。
I was wondering what the cause and effect of just talking about CpG density and life expectancy was, but when CpG → number of transition factors → genome size, I thought it would lead to a genome size that might be related to life expectancy.
マクロジェンからPacBio Revioの正式な案内が届きました。Novogeneの1ラン90万円に対して、マクロジェンは50万円程度になるようです。頼むならマクロジェンのほうが良さそうです。
=================================
来週からRevioサービスを開始いたします。
1cell当たり ~90GbのHiFi readを生産する内容です。
※保証ではありません。
価格は
64,000(library製作)+ 425,000(1cellラン)+ 20,000(HDD)=
509,000円(税別)
We have received official information about PacBio Revio from Macrogen.It seems that it will be about 500,000 yen for Macrogen compared to 900,000 yen for Novogene's run.Macrogen seems to be better if I ask.
=================================
We will start the Revio service next week.
This is the production of HiFi read from ~90Gb per cell.
*It is not a warranty.
at the price of
64,000 (library manufactured) + 425,000 (1cell run) + 20,000 (HDD)=
509,000 yen (tax excluded)
重要かどうかあまり分かっていませんが、寿命・老化関連で2つ見つけたので共有します。
Distinct longevity mechanisms across and within species and their association with aging - Cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867423004762
重要かどうかあまり分かっていませんが、寿命・老化関連で2つ見つけたので共有します。
種間および種内における異なる長寿メカニズムとそれらの老化との関連性 - 細胞
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867423004762
DNA methylation rates scale with maximum lifespan across mammals - bioRxiv
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.05.15.540689v1.full
DNAメチル化率は哺乳類全体の最大寿命とともに増加する - bioRxiv
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.05.15.540689v1.full
- 溝端秀彬
- 重要かどうかあまり分かっていませんが、寿命・老化関連で2つ見つけたので共有します。
Distinct longevity mechanisms across and within species and their association with aging - Cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867423004762
哺乳類の種による寿命の違い、老化、抗老化を網羅する重要なデータと思います。DNAメチル化と合わせて、遺伝子発現制御の種による違いや老化による変化が大事ということですかね。
CpG、トランスポゾン、ゲノムサイズ、寿命、いろいろ関連しそうに思います
I think it is an important data that covers the differences in life expectancy, aging, and anti-aging among mammalian species.Along with DNA methylation, differences in gene expression control depending on the species and changes due to aging are important.
CpG, transposon, genomic size, life expectancy -- all sorts of things
miniBUSCO: 通常のBUSCOよりも14倍速く、検出漏れが少ないBUSCO。通常のBUSCOだとT2T-CHM13のスコアが95.7%しかないが、miniBUSCOだと99.6%検出できたそう。(大量のゲノムを解析したい場合や完全に近いゲノムでなければ普通ので良いかもしれませんが)
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.03.543588v1
miniBUSCO: BUSCO is 14 times faster and less missed than normal BUSCO. Normal BUSCO has a T2T-CHM13 score of only 95.7% but miniBUSCO has 99.6% (if you want to analyze large numbers of genomes or if you don't have a completely close genome, it might be good)
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.03.543588v1
時間がかかり精度的に劣るaugustusによる遺伝子予測をしないで、直接miniprotで遺伝子をゲノムに張り付けて遺伝子予測するというアルゴリズムみたいですね。遺伝子予測した中に調べたい遺伝子がないとき、ゲノムにblastすると見つかることはよくあるので、miniBUSCOのほうがよさそうな気はします。
It seems to be an algorithm that predicts genes by attaching them directly to the genome with miniprot instead of predicting genes by Augustus, which takes time and is inferior in accuracy.When there is no gene you want to investigate in the genetic prediction, it is often found by blasting the genome, so I think miniBUSCO would be better.
頭足類の神経系でRNA編集が活発ということは以前読んだことがありましたが、、、
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(23)00540-8
I've read before that RNA editing is active in the cephalopod nervous system,,,
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(23)00540-8
核酸以外の生体物質はNGSで解析することができないため、metabolomicsにおいては複雑な実験系が必要ですが、これらの存在量を通常のscRNA-seq等のプラットフォームで多重的解析可能にできそう、というプレプリント。標的リガンドと結合すると蛍光を発するようになるstructure-switching aptamerから着想を得て、リガンドと結合するとバーコード付きオリゴを放出するようなaptamerを設計した、というアイデアのようです。異なるターゲット分子を認識するaptamerに異なるバーコードを持たせれば、複数の生体物質の存在量を同時にNGSで明らかにできそうです。
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.09.544402v1
Since biomaterials other than nucleic acids cannot be analyzed by NGS, a complex experimental system is required for metabolomics, but these presence amounts can be multiplexed on platforms such as regular scRNA-seq.Inspired by a structure-switching aptamer that emits fluorescence when combined with a target ligand, the idea seems to be to design an aptamer that releases oligos with barcodes when combined with a ligand.If aptamers that recognize different target molecules have different barcodes, NGS will be able to reveal the amount of multiple biomaterials present at the same time.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.09.544402v1
TTXの蛍光aptamerは既に開発されているようなので、↑が使えるなら細胞毎の毒量を反映したscRNA-seqができるかもしれませんね
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142519304494?via%3Dihub
TTX fluorescent aptamer seems to have already been developed, so if ↑ can be used, scRNA-seq may be able to reflect the amount of poison per cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142519304494?via%3Dihub
TTXで使えそうと思い、後で読もうと思ってました。
溝端君が言うようにアプタマーの論文がいくつかあるので、しっかり読んでやれそうか検討したいと思います。
I thought I could use it on TTX, so I was going to read it later.
As Mr. Mizubata said, there are several Aptamer papers, so I would like to consider whether I can read them carefully.
あとこれは僕にしか関係ないんですが、今投稿中のやつとちょっとだけ被った論文が出ててショックです笑
そこまで詳しく調べてないし盗刺胞メインではあるんですが、僕のbioRxivより5日早く出てます
https://link.springer.com/article/10.1134/s0012496622700181
Also, this is only related to me, but I'm shocked to see a little bit of the paper that I'm posting now
I haven't looked into it that much, and although the main one is stolen cells, it came out 5 days earlier than my bioRxiv
https://link.springer.com/article/10.1134/s0012496622700181
死んだ個体と一緒にすごしていると寿命が短くなる、、、、
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002149
If you live with a dead individual, your life will be shortened,,,,
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002149
先の土曜日に東京大学生命科学シンポジウムに出てきました。
https://www.todaibio.info/
多様な発表が程よい数で聞けるのと、発表は院生が中心で学生表彰が充実しているので、学生は積極的に参加してはどうかと思いました。
部分的にしか話しを聞けなかったのですが、その中で幾つか。
1.植物の幹細胞は動物細胞よりも多能性に優れるのですが、それを支えるメカニズムとして、RNAの品質管理(転写、スプライシング、分解)が大事だそうです(大谷美沙都先生)。mRNAの分解スピード(半減期)を網羅的に解析するERIC-seqという手法が使われていました。許さんのmRNA ageはこうした手法で検証できるのではと思いました。
2.ヒストンの特定の位置にアセチル化を起こす化学触媒系(PEG,アセチルCoA,CPP,などの複合体)の発表がありました(川島茂裕先生)。これにより、特定のガン細胞の増殖を抑制するなど、実際の応用が可能になっているようです。
3.クライオ電顕で、酵素、クロマチン、ヌクレオソーム等の構造を3次元的に解析する発表が幾つかありました。結晶構造解析とは違うアプローチで、分子レベルの3次元像が得られるクライオ電顕は東大で共通機器でも使えるようです。
4.先の論文でもありましたが、クラゲの再生時の幹細胞のタイプ分けの発表がありました(中嶋先生グループ)。エダアシクラゲの足の再生時には、新しい幹細胞集団が現れますが、これは脱分化した体細胞ではなく、休眠していた幹細胞ではないかとのことでした。ただし、実験的な検証はありませんし、ベニクラゲがどうかは不明です。
I attended the University of Tokyo's Symposium on Life Sciences last Saturday.
https://www.todaibio.info/
I thought that students should actively participate because various presentations can be heard in a moderate number and the presentation is mainly made by graduate students and the student awards are substantial.
I could only listen to some of them in part.
1. Plant stem cells are more pluripotent than animal cells, but RNA quality control (transcription, splicing and decomposition) is important as a support mechanism (Mr. Misato Otani). ERIC-seq was used to comprehensively analyze the speed of mRNA degradation (half-life).I thought Mr. Heo's mRNA age could be verified in this way.
2. Chemical catalysts (complexes such as PEG, acetyl CoA, CPP) that cause acetylation at specific locations of histones have been announced (Mr. Shigahiro Kawashima), which seems to be enabling practical applications such as inhibiting the growth of certain cancer cells.
3. There have been several announcements in cryoelectronics that analyze the structure of enzymes, chromatin, nucleosomes, etc. in three dimensions.Using a different approach from crystal structure analysis, cryoelectron, which can obtain three-dimensional images at the molecular level, seems to be usable in common equipment at Tokyo University.
4. As mentioned in the previous paper, there was an announcement on the categorization of stem cells during jellyfish regeneration (Dr. Nakajima group). When jellyfish legs are regenerated, a new stem cell population appears, but not dedifferentiated somatic cells.However, there has been no experimental verification and it is not known what about safflower jellyfish.
我々真核生物の起源はアスガルド古細菌(上門)という古細菌であると考えられています。2015年に熱水噴出口から最初のアスガルド古細菌であるロキ古細菌が発見されて以来、トール、オーディンなど北欧神話にちなんだ古細菌門が報告されてきましたが、どれが真核生物と最も近縁なのかは分かっていませんでした。この研究では、既知のアスガルド古細菌に加えて世界11箇所から新たに63個のアスガルド古細菌由来のMAGを同定し、網羅的な系統解析を行ないました。その結果、真核生物はヘイムダル古細菌門の中から誕生したと考えられることが分かりました。
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06186-2
We eukaryotes are thought to have originated from an archaebacterium called Asgard Archaea (upper gate).Since the discovery of Loki Archaea, the first Asgardian archaea, in 2015 at hydrothermal vents, archaea phylum related to Norse myths such as Thor and Odin have been reported, but it was not known which was most closely related to eukaryotes.In this study, 63 new Asgardian-derived MAGs were identified from 11 locations around the world in addition to known Asgardian archaebacteria, and a comprehensive phylogenetic analysis was conducted.The results showed that eukaryotes were thought to have originated from the Haemdal Archaea.
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06186-2
仲間の死体を’見る’と寿命が短くなる。
https://www.nature.com/articles/s41467-019-10285-y
If you 'see' a companion's body, your life will be shortened.
https://www.nature.com/articles/s41467-019-10285-y
この件は、見ることがポイントかはわからないけど、銀ブナで体験済みです。短くというのではなく、釣られ死します。死因がまず水質とかではないので、とても不思議ですね。メンタルかもしれないし、そのメンタルのつながり方が視覚なのかどうかもわかりませんが。
I don't know if this is the point, but I have already experienced it with a silver beech.It's not short, it's caught and killed.The cause of death is not water quality, so it's very strange.It may be mental, and I don't know if the mental connection is visual or not.
G400は4レーン以上というのがネックです… 普通にG400を頼めば1レーンからだったと思います。
The problem with the G400 is that it has more than 4 lanes...I think it would have been from 1 lane if I ordered the G400.
・1レーン当たりのミックスする上限の制限はない。(1000サンプルでも問題ない)
・PE300は片側300bpの合計600bp!
・Illuminaのライブラリーだとしても、インデックスの変換は行わず、末端をリン酸化させるだけで、シーケンスプライマーにIlluminaのものを使う!
今まで特許侵害から口を閉ざしていたような印象でしたが、今回のウェビナーで気になっていた点が明らかになりました。MiFish用にはとても良さそうなシーケンサーだと思います。
·There is no limit to mixing per lane.(1000 samples is fine)
·PE300 has a total of 600bp, 300bp on one side!
·Even if it is Illumina's library, it does not convert indexes, just phosphorylates the end, and uses Illumina's as a sequence primer!
I had the impression that I had kept my mouth shut from patent infringement until now, but this webinar revealed something that bothered me.I think it's a very good sequencer for MiFish.
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
Visiumの高解像度版はまだ登場しませんが、Broad Institute発のSlide-Seqをベースにした10 um解像度のSpatial Whole Transcriptome解析を可能にするCurio Seekerという製品がCurio Bioscience社から販売されたそうです。
日本の販売店は下記になるようで、8スライド220万円だそうです。(Visiumと同じくらいの価格?)
https://www.biostream.co.jp/
製品のウェビナー
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8_2GWGq0Q
開発元
https://curiobioscience.com/
Although a high-resolution version of Visium has not yet appeared, Curio Seeker, which enables 10um resolution spatial Whole Transcriptome analysis based on Slide-Seq from Broad Institute, has been sold by Curio Bioscience.
The store in Japan is as follows, and it costs 2.2 million yen for 8 slides (about the same price as Visium?)
https://www.biostream.co.jp/
Product Webinars
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8_2GWGq0Q
manufacturer
https://curiobioscience.com/
Single cell longread
https://www.nature.com/articles/s41467-023-40898-3#Sec11
全ゲノム増幅の方法がdMDA(droplet-based multiple displacement amplification)
を用いることで増幅のバイアスを抑えたことにより、PACBIOに供しても問題ないゲノムを取得しているみたい。
Single cell longread
https://www.nature.com/articles/s41467-023-40898-3#Sec11
The method of whole genome amplification is dMDA (droplet-based multiple displacement amplification)
By suppressing amplification bias by using , it seems that the genome is obtained without any problems for PACBIO.
読んでませんがMDAについては以下の論文です
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.082089499
I haven't read it, but the MDA is as follows
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.082089499
新しく参加したメンバーも参加以前のトーク内容を確認できます。
活性酸素ストレスなどの寿命の長短に影響するカスケードはよく知られているが、そのスイッチは様々、、、
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2023/pr20230927/pr20230927.html
Cascades that affect the length of life such as active oxygen stress are well known, but the switches vary,,,
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2023/pr20230927/pr20230927.html
DNBSEQのウェビナーを見ていると、DNBSEQのindex hopping率が公式に出てました。
Looking at the DNBSEQ webinar, the index hopping rate of DNBSEQ was officially announced.
改訂版RNA-Seqデータ解析 WETラボのための超鉄板レシピ ヒトから非モデル生物まで
https://amzn.asia/d/dU2g3p9
を購入しました。RNA-seqをこれからしないといけない人、解析に興味のある人で勉強会でもしようかなと思うのですが、希望者はいますか?本に書いているコマンドを10ー20個実行して、結果どうだったかを共有するというのを7回くらいのボリュームで考えています。
具体的には本の中の
HISAT2
STAR
TRINITY
SALMON
TCC
FanflowInsects
階層的クラスタリング
あたりを実際に動かしてみるという感じです。
Revised RNA-Seq Data Analysis Super Steel Recipe for WET Lab From Human to Non-Model Organisms
https://amzn.asia/d/dU2g3p9
has been purchased.I'm thinking of having a study session with people who need to do RNA-seq from now on, and people who are interested in analysis. Is there anyone who wants to do it?I'm thinking of executing 10-20 commands in a book and sharing the results with you about 7 times.
Specifically, it's in the book
HISAT2
STAR
TRINITY
SALMON
TCC
FanflowInsects
hierarchical clustering
It's like actually moving around.
- Kazutoshi Yoshitake
- 改訂版RNA-Seqデータ解析 WETラボのための超鉄板レシピ ヒトから非モデル生物まで
https://amzn.asia/d/dU2g3p9
を購入しました。RNA-seqをこれからしないといけない人、解析に興味のある人で勉強会でもしようかなと思うのですが、希望者はいますか?本に書いているコマンドを10ー20個実行して、結果どうだったかを共有するというのを7回くらいのボリュームで考えています。
具体的には本の中の
HISAT2
STAR
TRINITY
SALMON
TCC
FanflowInsects
階層的クラスタリング
あたりを実際に動かしてみるという感じです。
フグ卵の遺伝子発現解析を今後やる予定なので参加希望します。
We are planning to analyze the gene expression of puffer fish eggs in the future, so we would like to participate.
サメの核DNAの変異率はこれまで調べられている脊椎動物で圧倒的に低い(ヒトの1/17)。集団としては多様性の維持・獲得が難しくなってしまうが、個体レベルではガンの発生率が低く、長命に寄与していることが考えられる
The rate of variation in the nuclear DNA of sharks is overwhelmingly low in vertebrates that have been examined so far (1/17 of humans).As a group, it becomes difficult to maintain and acquire diversity, but at the individual level, the incidence of cancer is low and contributes to long life
ちなみにサメは入っていませんが、脊椎動物17種のDNA変異率を調べたものがこちら。脊椎動物の中では魚類の変異率は低いそうです
By the way, there are no sharks in it, but here's a DNA study of 17 vertebrates that says fish have a low rate of variation
ナノポアの最新状況を聞けるセミナーが11月24日にあるのですが、私と米澤くんは参加できないので、もし参加できるなら是非参加してどういう発表があったか教えてください。
https://nanoporetech.com/about/events/seminars/springer-protocol-book-seminar
There will be a seminar on November 24 where I can ask about the latest status of nanopore, but Yonezawa-kun and I cannot participate, so if you can, please attend and let me know what kind of announcement was made.
https://nanoporetech.com/about/events/seminars/springer-protocol-book-seminar
ワシントン大学の今井先生が一時帰国して講演会するみたいです。
セミナーの日と被っているので難しいと思いますが、一応情報としてシェアしておきます。
https://1204conference.peatix.com/event/3723817/view?utm_campaign=pod-11706967&utm_medium=email&utm_source=follow-organizer&utm_content=17249368&dlvid=4a1e8f40-07b5-424e-9f6d-7c82db0a2bee&sltid=0
It seems that Dr. Imai of Washington University will return to his country temporarily and give a lecture.
I think it will be difficult because it is the day of the seminar, but I will share it with you as information.
https://1204conference.peatix.com/event/3723817/view?utm_campaign=pod-11706967&utm_medium=email&utm_source=follow-organizer&utm_content=17249368&dlvid=4a1e8f40-07b5-424e-9f6d-7c82db0a2bee&sltid=0
大阪現地開催なので現実的ではありませんが、老化や寿命に関する研究をしている人にはリンクの参考情報だけでも有用だと思います。
https://peatix.com/event/3737746?utm_medium=web&utm_content=3737746&utm_source=related%3A3723817&utm_campaign=related
It's not realistic because it's held in Osaka, but I think the reference information on the link is useful for people who are researching about aging and life expectancy.
https://peatix.com/event/3737746?utm_medium=web&utm_content=3737746&utm_source=related%3A3723817&utm_campaign=related
宮本さんのTwitterを見て、酵素減らして時間伸ばすプロトコル気になっていたので助かります
Looking at Miyamoto's Twitter account, I was concerned about the protocol to reduce enzymes and extend time, so it is helpful
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28454-x
L. pneumophila RNAs can be transported within extracellular vesicles (EVs) into the host cell where they are biological active and can modulate the host immune response in a miRNA-like manner.
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28454-x
L。 肺炎フィラRNAは、細胞外小胞(EV)内で生物学的に活性な宿主細胞に輸送することができ、miRNAのような方法で宿主免疫応答を調節することができる。
ついにVisium HDがリリースされるようですね。今までのVisiumと違って、スライスした組織をガラスに張り付ける専用の装置が必要になるようなので、Visiumも外注が主流になるのでしょうか。解像度がとても高い分、シーケンスいくらするのだろう。
https://www.10xgenomics.com/jp/products/visium-hd-spatial-gene-expression?utm_medium=email&utm_source=internal&utm_term=es-2024-01-tech-lit-vis-sp-visium-hd-launch-promo&utm_content=technical-literature&utm_campaign=701KW000001974zYAA&mktouserid=121231&mkt_tok=NDQ2LVBCTy03MDQAAAGQqbaOzDettD8CUnsSEsvm87kkiQHTFNbheYwvYmnLyDffSbOeRYAFgMhwLIgiTqvCo-HGnmgr2uLqYBEUa5MFY7Af72EXFusXH-zhXGFWweal
It looks like Visium HD will finally be released.Unlike previous Visiums, there seems to be a need for specialized equipment to stick sliced tissue to glass, so will Visium become more outsourced?I wonder how much the sequence will cost because the resolution is so high.
https://www.10xgenomics.com/jp/products/visium-hd-spatial-gene-expression?utm_medium=email&utm_source=internal&utm_term=es-2024-01-tech-lit-vis-sp-visium-hd-launch-promo&utm_content=technical-literature&utm_campaign=701KW000001974zYAA&mktouserid=121231&mkt_tok=NDQ2LVBCTy03MDQAAAGQqbaOzDettD8CUnsSEsvm87kkiQHTFNbheYwvYmnLyDffSbOeRYAFgMhwLIgiTqvCo-HGnmgr2uLqYBEUa5MFY7Af72EXFusXH-zhXGFWweal
きれいな切片を作って正確に張り付ける、というところがとても重要かつハードルが高いので、外注になるならその方が良いのかもしれません。データ量が莫大になりそうなので、シーケンス費用は気になるところですね。それも含めてトータルの費用がすごそう
Making a clean section and pasting it accurately is very important and has high hurdles, so if you want to outsource it, that might be better.The amount of data is going to be huge, so I'm worried about the sequence cost.Including that, the total cost seems to be great
Visium HDのウェビナーを聞いていますが、リード数は10億リード程度で十分ということらしく、リード数自体は今までのVisiumと比べてそんなに増えることはなさそうです。
Visium HDは1スポットのサイズが2um x 2umで、1スポットあたり100UMI程度の検出数になるようです。
I've been listening to the Visium HD webinar, and it seems that about 1 billion leads is enough, so the number of leads themselves is unlikely to increase much compared to previous Visiums.
Visium HD has 1 spot size of 2um With x2um, it seems that the number of detections is about 100UMI per spot.
Visiumという名前だけど、ヒト、マウス用に設計されたプローブをハイブリさせるそうで、ヒト、マウス以外には使えないらしい・・・
It's called Visium, but it seems that it can only be used for humans and mice because it hibbles probes designed for humans and mice...
Galaxy:HiFi, Hi-C, Bionano等のデータセットを使用して高精度なゲノムをアセンブルする自動パイプライン
https://doi.org/10.1038/s41587-023-02100-3
Galaxy: An automated pipeline that assembles high-precision genomes using data sets such as HiFi, Hi-C, and Bionano
https://doi.org/10.1038/s41587-023-02100-3
以降は下記のFacebook Messengerへ
https://www.facebook.com/messages/t/6765452673531366
From now on, please visit Facebook Messenger below
https://www.facebook.com/messages/t/6765452673531366
Groups note

ノート活用ガイド
ノートはトークルーム内のメンバーのみが投稿/閲覧できる情報共有スペースです。
このトークルームに関連する業務内容や引き継ぎ事項を投稿しておけば、各メンバーがいつでも確認できます。

お知らせ
重要な投稿は「お知らせに表示」を設定すれば、トークルーム内の上部で表示されます。
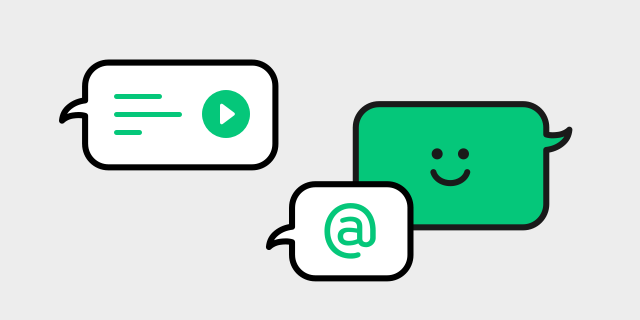
便利な機能
「編集許可」に設定すると、メンバーは閲覧だけでなく投稿を更新できます。
マニュアルや機能説明にも動画添付をしたり、ファイル添付やスタンプ、メンションなどの機能で、より円滑な情報共有も可能です。

共有
トークルームでの情報共有にはノートを、より広範囲な情報共有には掲示板サービスを活用しましょう。
「他のノートにコピー」「掲示板にコピー」から簡単に投稿を複製できます。


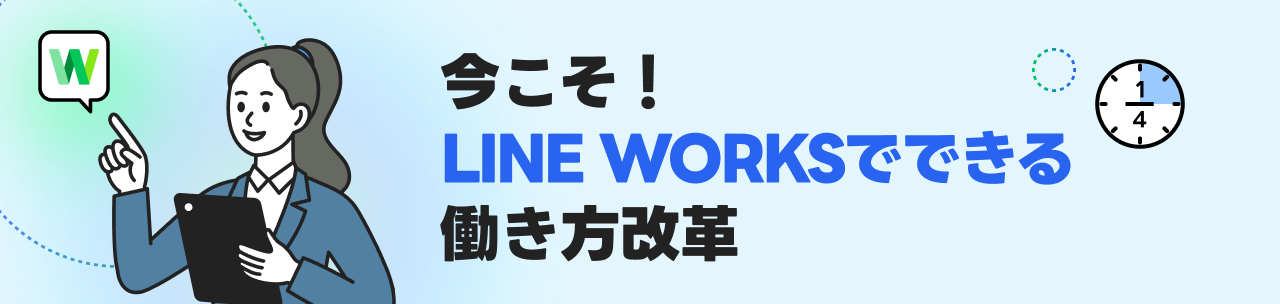





 進行中
進行中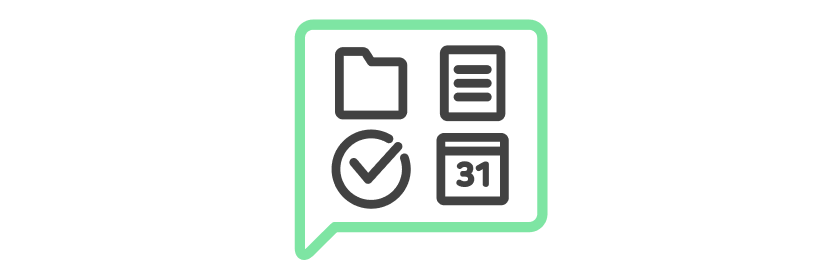 複数人のトークルームでも
グループ機能が使えます!
複数人のトークルームでも
グループ機能が使えます!